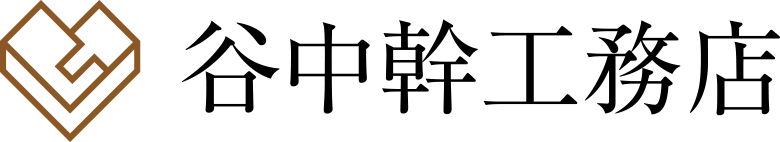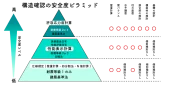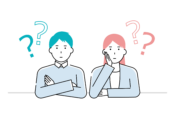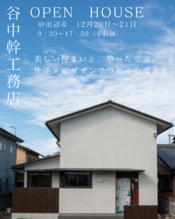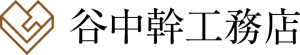「失敗しない断熱材選び」グラスウールとロックウールの違いをわかりやすく解説!

「うちの断熱材、これで本当にいいのかな?」
そんな風に不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
近年、断熱材は住まいの“快適さ”や“省エネ性能”を支える重要なものとして、注目が高まっています。特にグラスウールとロックウールはよく使われる素材ですが、同じウール系ですし、「違いがよくわからない」「何を基準に選べばいいの?」という声をよく耳にします。
和歌山県田辺市の木の家専門工務店、谷中幹工務店です。この記事では、2つの素材の特性を比較解説し、難しい専門用語も出来るだけかみ砕いてお伝えしてきます。
「グラスウールとロックウール、どっちを選ぶべき?」その迷いの解決の一助になれば幸いです。
また、自分の家や使う場所に合った断熱材を見極める力が身につき、冷暖房効率や快適性の向上、さらには光熱費の節約にもつながっていきます。
グラスウールもロックウールも、それぞれに強みがあります。大切なのは、場所や目的に合った“上手な使い分け”。記事を通じて、あなたにぴったりの選び方が見えてくるはずです。
1. グラスウールとロックウールの基礎知識

1‑1. グラスウールとは?原材料と製造方法
グラスウールとは、ガラスを原料として製造された繊維状断熱材で、「ガラス繊維」を綿のように束ねた構造を持ち、空気を閉じ込めて高い断熱性能を発揮します。
製造工程では、砂やリサイクルガラスを溶融し、高速遠心紡器(いわゆる「綿菓子製造機」状の装置)を用いて繊維化し、バインダーで繊維を接着した後、ロールや板状に成形されます。
この構造により、多数の小さな空気層が形成され、空気の伝導率の低さを活かして優れた断熱性を得ることができます。
用途としては、ロール状やバット(断熱マット)として壁や天井、床下、配管の断熱や吸音材として広く使われています。
ただし、施工時に皮膚や目への刺激が生じる可能性があり、適切な防護具の着用が推奨されます。
1‑2. ロックウールとは?原材料と製造方法
ロックウールは玄武岩やダイアベースなどの天然の火山岩を高温で溶かし、同様に高速遠心紡により繊維化して形成される断熱・吸音材で、その製造プロセスはグラスウールと技術的には類似しています。
高密度で耐久性が高く、特に高温や防火性能が求められる環境への適応能力に優れます。
また、吸音性にも優れており、音を吸収する能力が高いため、防音対策として音響パネルやコンクリート間の遮音層にも使用されています。
製品形態としては板状、ロール、吹き込み用など多様で、建築・産業用断熱、防火層、吸音層として幅広い用途に対応します。
リサイクル性に優れ、溶かして繰り返し再生できるため、環境面でも高評価を得ています。グラスウールも同様にリサイクル性に優れています。
1‑3. 主な用途と適材適所の違い
グラスウールは軽量性や柔軟性が高く、住宅の壁や床、天井などの一般的な断熱ニーズに対し幅広く使われています。
反対に、ロックウールは高い密度と耐火性を活かして、工業設備、外壁、火災隔壁など高温・耐火性が求められる用途に適しています。
また吸音性能の差から、防音室やスタジオ、集合住宅の遮音壁など、音の制御が重要な場面ではロックウールがよく使われます。
グラスウールは価格面でも優位であり、その点でもの住宅リフォームや新築工事で選ばれる傾向が強いです。
一方、厳しい防火基準や工場用途などでは、価格が高くとも性能重視でロックウールが選択されます。
1‑4. 両者の歴史と普及の背景
グラスウールは1933年にアメリカで開発され、特許も取得されており、その歴史は比較的古く、広範に普及してきました。
市場においては、住宅用断熱材としてその軽さと価格の手頃さから一般的に広く利用されてきました。
ロックウールは産業用途や高温用途でのニーズから発展し、特に耐火性や吸音性に優れる性質が注目されて市場を拡大しています。
両素材とも鉱物を原料にするという共通点があり、非可燃性(A1等級)として防火規制の対象にも適合します。
また、環境配慮の流れからいずれも高いリサイクル率やエコ認証への対応も進んでいます。
1‑5. 安全性と健康への影響比較
両素材ともミネラルウールに属し、IARC(国際がん研究機関)によれば、グラスウールもロックウールも「ヒトに対して発がん性が分類されない(Group 3)」とされています。
ただし、施工作業中に微細な繊維が飛散することで、皮膚や目に刺激を引き起こす可能性があります。
したがって、施工時にはマスクやゴーグル、長袖などの保護具の着用が義務付けられています。
グラスウールの方が施工時に繊維が飛散しやすいとも言われています。ロックウールは密度が高いためやや飛散しにくい面もありますが、それでも十分な防護措置は必要です。
2. グラスウールとロックウールの違い

2-1. 断熱性能の違いとその理由
グラスウールとロックウールはいずれも断熱材として広く使用されていますが、その断熱性能には製品ごとにわずかな違いが存在します。特に、熱伝導率(λ値)という指標を用いることで、両者の断熱性能を比較することができます。
一般的に、グラスウールの熱伝導率は製品の密度によって異なり、低密度タイプ(例:10K程度)では0.050W/m·K程度、高密度タイプ(例:24K〜40K)では0.038〜0.033W/m·K程度となります。これは密度が高いほど空気層が多くなり、熱を伝えにくい性質を持ちます。
特に、高性能グラスウール16K製品は、一般的な住宅の断熱施工で多用され、熱伝導率は0.038W/m·Kとされます。これはロックウールとほぼ同等の断熱性能であり、コストパフォーマンスに優れる点から支持されています。
一方でロックウールは、その構造上比較的高密度な製品が主流であり、一般的な熱伝導率は0.038〜0.040W/m·K程度です。標準的なグラスウールと比較すると、やや優れた断熱性能を持つ製品が多い傾向にありますが、前述のような高性能グラスウール製品と比べた場合には同等といえます。
断熱性能の違いを決定づけるのは、素材の種類そのものよりも「密度」や「構造」による影響が大きく、適切な選定と施工がなされていれば、どちらを選んでも十分な断熱効果を得ることができます。
つまり、断熱性能においてはグラスウールとロックウールの「素材そのものの優劣」ではなく、「製品グレードの選定(密度や熱伝導率)」が性能差の決め手になります。価格や設計条件を踏まえた上で、最適なスペックの製品を選ぶことが重要です。
2-2. 吸音・防音性能の比較
グラスウールとロックウールはともに繊維系の素材であり、吸音材としての性質を持ちますが、その性能には明確な違いがあります。特に密度と繊維の構造が、音の吸収能力に大きな影響を与えます。
ロックウールは一般的に高密度で繊維が太く、音波を内部で複雑に反射・減衰させる構造を持っています。このため、特に中〜高音域の吸音性能に優れており、防音壁や音響スタジオ、機械室などに多用されています。
一方、グラスウールは繊維が細かく軽量なため、比較的低密度でも吸音効果が得られるのが特徴です。住宅の天井裏や壁内部、床下など、幅広い場所で利用され、特に日常的な生活音への対応に適しています。
ただし、遮音性(音を遮る力)に関しては、グラスウールもロックウールも単独では限界があり、石膏ボードや遮音シートとの組み合わせによって効果を発揮します。吸音=防音ではないことを理解することが大切です。
総じて言えば、防音性能を高めたい場合には、より密度が高く吸音能力の強いロックウールが優位であり、コストや施工性を重視するならグラスウールが適しているといえます。用途と目的に応じた適切な選択が求められます。
2-3. 耐火性能と防火対策としての活用
グラスウールとロックウールはどちらも無機質系断熱材であり、基本的に「不燃材料」に分類されます。建築基準法においても、両者とも耐火建築物に使用可能な材料とされています。
特にロックウールは、火山岩を主原料とし、非常に高い耐熱温度(約1,000℃)を持つため、防火・耐火性においては優れた性能を発揮します。そのため、火災時の延焼防止対策として、設備室やファサード、耐火壁の断熱材に多く採用されています。
一方、グラスウールも耐熱温度はおよそ500~700℃とされ、通常の住宅火災においては十分な耐火性能を有しています。ただし、ロックウールと比較すると高温域での安定性や収縮の面ではやや劣るとされます。
耐火構造を必要とする場合、国土交通省認定の耐火認定番号が付与された製品を使用することが求められます。グラスウール・ロックウールともに、このような認定を取得している製品が多く流通しています。
総合的に見ると、より厳しい耐火性が要求される場面ではロックウールの方が安心感がありますが、一般住宅や準耐火構造ではグラスウールでも十分に対応可能です。建物の構造種別や設計条件に応じた選定が重要です。
2-4. 施工のしやすさと現場での扱い
断熱材を選定する際、性能と同じくらい重要なのが「施工性」です。いくら性能が高くても、現場での施工が難しかったり手間がかかると、結果として断熱効果が不十分になったり、工期やコストに影響を与えることがあります。
グラスウールは軽量で柔軟性が高く、切断やしやすく施工性が高い為、住宅施工現場では非常に扱いやすい素材とされています。ロール状やマット状に加工されている製品も多く、複雑な構造部分にも対応しやすいのが特徴です。
一方、ロックウールは高密度かつ剛性が高いため、カットや加工にはやや力が必要です。また、繊維の太さから扱う際にややチクチクする感覚があり、手袋や長袖の着用が欠かせません。その分、しっかりとした形状保持力があり、一定の場所に固定しやすいという利点もあります。
また、ロックウール製品はグラスウールに比べて一般的に「長さが短い」傾向があります。これは製造時の寸法安定性や運搬性を重視した仕様であり、特に広い面積を連続して施工する場合には接合部が増える可能性があります。施工効率に影響するため、現場ごとの事前確認が重要です。
飛散性の違いにも注目すべきです。グラスウールは軽いため施工時に細かい繊維が空中に舞いやすく、防護メガネやマスクの着用が推奨されます。ロックウールも同様の注意は必要ですが、密度が高いため比較的飛散しにくい傾向があります。
結論として、いずれにしても、断熱性能を最大限に引き出すためには施工精度の高さが不可欠であり、施工者の技術力や現場環境に応じた適切な素材選びと丁寧な施工が求められます。
2-5. 環境性能とリサイクル性の違い
近年、建築業界では「断熱性能」だけでなく「環境性能」も重視されるようになってきました。特に断熱材は大量に使用されるため、その製造・使用・廃棄の過程での環境負荷が注目されています。
グラスウールは主にリサイクルガラスや天然のけい砂を原料としており、比較的環境負荷の少ない素材とされています。国内外の多くのメーカーがリサイクル率の高い製造プロセスを採用しており、エコマークやLEED認証にも対応した製品が増えています。
ロックウールも天然の火山岩などを原料とする無機鉱物系の素材であり、こちらも再資源化が可能です。特に産業系建築物や公共建築では、ロックウールのリサイクル性と長寿命性が高く評価されています。
燃焼時の有毒ガス発生がないことも、両素材に共通する大きな環境メリットです。火災時の安全性に加えて、ライフサイクル全体を通じたCO₂排出削減効果も見込まれています。
ただし、製造時のエネルギー消費量という面では、ロックウールの方がやや高い傾向にあるとされます。一方でグラスウールは軽量な分、輸送時の環境負荷が低く、全体としてのカーボンフットプリントに優れる場合があります。
環境性能においては、どちらが優れているかは一概に言えず、製品の設計・供給体制・使用条件によって判断すべきです。環境配慮型住宅や公共事業では、各製品の環境ラベルや第三者認証を確認することが推奨されます。
3. 目的別の選び方と今後の展望

3-1. 一戸建て住宅に最適な選び方
一戸建て住宅において断熱材を選ぶ際には、断熱性能はもちろん、コスト、施工性、将来のメンテナンス性など、さまざまな視点から総合的に判断する必要があります。中でも、断熱性能と施工しやすさのバランスが重要です。
一般住宅で最も多く採用されているのが「高性能グラスウール(16K)」です。このタイプは、断熱性能(熱伝導率0.038W/m·K程度)がロックウールと同等で、コストも比較的抑えられており、壁や天井などに使用されています。
グラスウールは柔軟性に優れ、狭小空間や変形箇所へのフィット性も高いため、施工者にとって取り扱いやすい素材です。ただし、断熱効果を最大限に発揮するには、隙間なく丁寧に施工する必要があり、熟練の施工技術と知識が求められます。
一方、火災リスクを重視する場合や外壁周りなどに強固な耐火層が求められる箇所では、ロックウールが適していることもあります。ただし、住宅規模であればグラスウールでも十分な耐火性能を発揮することが多いです。
総じて言えば、一戸建て住宅では「コストパフォーマンスに優れ、扱いやすい高性能グラスウール」を中心に選び、必要があれば(あればですが・・・)「ロックウールを補助的に使う」という考え方が現実的です。使用部位や目的に応じて素材を使い分けることで、快適性と耐久性を両立する家づくりが可能になります。
3-2. 用途に応じた断熱材の賢い使い分け方
断熱材の選定は、建物の構造や用途によって最適なものが異なります。住宅、商業施設、工場、倉庫など、それぞれが求める性能や施工条件が異なるため、「一律の正解」が存在しないのが実情です。だからこそ、用途に応じた「賢い使い分け」が重要です。
たとえば、住宅では断熱性と施工性、コストパフォーマンスのバランスが重視されるため、グラスウールが多く採用されます。一方で、大空間のある商業施設では遮音性能や天井裏の断熱、さらには耐火性が求められるケースが多く、ロックウールが選ばれることがあります。
工場や倉庫などでは、火災時のリスク管理や設備周辺の耐熱対策が重視されるため、ロックウールの高い耐火性と形状保持力が評価されます。特に電気室やボイラー室周辺など、高温になりやすい場所ではロックウールの使用が一般的です。
逆に、短期的な使用や仮設建物など、初期コストを抑えたい現場では、一般的な密度(10K前後)のグラスウール製品が有効です。長期的な耐久性よりもコスト重視の場面で選ばれることが多く、用途に応じた柔軟な選択が求められます。
結論として、グラスウールとロックウールは「どちらが優れているか」ではなく、「どこで使うか」「どう使うか」でその真価が変わる素材です。建物の目的・使用環境・メンテナンス方針などを踏まえた上で、最適な組み合わせを選ぶことが賢明な選択といえるでしょう。
3-3. 価格帯とコストパフォーマンス比較
断熱材の選定において、性能と同様に重要視されるのが「価格帯」と「コストパフォーマンス」です。特に住宅建築や中小規模の施設では、初期コストを抑えながらも十分な性能を確保することが求められるため、断熱材の価格と性能のバランスは慎重に見極める必要があります。
一般的に、グラスウールはロックウールよりも安価です。たとえば、同等の厚み・サイズ・断熱性能を持つ製品で比較した場合でも、グラスウールはおおよそ1割〜2割程度低価格であるケースが多く、コストを重視する現場での採用率が高いです。
一方で、ロックウールは製品自体の単価が高めであり、施工時のカット性や重量面でも手間がかかるため、トータルの施工費が高くなる傾向があります。ただし、耐火性や吸音性など、付加価値の高さを重視する場合には、その価格差に見合うメリットがあると考えられています。
また、高性能グラスウール(高性能16Kや24Kなど)は、標準品より価格は上がりますが、断熱性能が高いため、冷暖房効率の向上やエネルギーコストの削減に繋がる「長期的な経済性」で優位に立つ選択肢とも言えます。初期費用とランニングコストの両面から比較することが重要です。
最終的には、「断熱性能だけでなく、施工の手間、耐久性、用途との相性」を総合的に見たときに、どちらの素材が最適かを判断するのが賢い選び方です。コストだけで選ぶのではなく、「価格に対して何を得られるか」という視点が、より満足度の高い選定につながります。
3-4. リフォーム時の選定ポイント
住宅のリフォームにおいて断熱材を選定する際には、新築とは異なる視点が求められます。既存の構造を活かしつつ性能を向上させる必要があるため、断熱材の「厚み」「柔軟性」「施工性」が大きなカギを握ります。
リフォームで断熱性能を向上させる場合には、「グラスウール」が有力です。中でも、高性能グラスウール(16Kなど)は、断熱性能と厚みのバランスが良く、さまざまな部位に柔軟に対応できることから、リフォーム市場でも広く活用されています。
リフォーム現場では、スペースの制限や既存設備との干渉が避けられないことも多いため、断熱材の寸法調整や切断のしやすさも重要です。その点で、グラスウールは柔軟性が高く、現場対応力のある素材として評価されています。
ただし、断熱材を入れ替える場合は、元の施工精度や湿気対策の確認も欠かせません。断熱材だけを交換しても、隙間があったり防湿層が不完全であれば、十分な効果が得られない可能性があります。適切な施工と現場状況の確認が、リフォーム成功の鍵となります。
防湿層気密層について詳しい記事はこちら
3-5. 今後注目される断熱材のトレンド
断熱材の世界でも技術革新が進んでおり、今後は性能だけでなく「環境対応」「施工効率」「健康・安全性」といった新たな視点からの選定が求められるようになってきています。単に断熱するだけではなく、持続可能性を重視した製品選びが注目されつつあります。
たとえば、グラスウールやロックウールなどの繊維系断熱材は、かつてはバインダーに微量のホルムアルデヒドを含んでいた製品もありました。しかし現在では、ノンホルムアルデヒドタイプの製品が各社から登場しており、シックハウス対策や室内空気環境の改善を意識した製品開発が進んでいます。安全性を重視する現場では、こうした選択肢が今後ますます重要になります。
環境面では、「カーボンフットプリント削減」への意識が高まっています。これは、断熱材の原料調達から製造、運搬、施工、廃棄に至るまでの全工程におけるCO₂排出量をできる限り抑えるという考え方です。特にグラスウールでは、リサイクルガラスの使用比率を高めることで、製品1本あたりの環境負荷を低減する取り組みが進められています。
施工現場では、作業の省力化や時間短縮を可能にするプレカット品、吹き込み工法、ボード型断熱材など、現場ニーズに応じた製品バリエーションも増加しています。労働力不足が深刻化する中、誰でも均一な品質で施工できる工法の需要が高まっています。
また、断熱性能の高性能化も進みつつあり、薄くても優れた断熱効果を発揮する高密度タイプや、真空断熱材、エアロゲル系断熱材などの新素材にも注目が集まっています。まだコスト面での課題はありますが、省スペース化が求められる都市型住宅などでは今後の有力な選択肢となるでしょう。
総じて、これからの断熱材は「高性能+環境対応+健康への配慮」という三本柱が重視される傾向にあります。グラスウールやロックウールも引き続き重要な位置を占めながら、それぞれが進化を遂げていくことが、今後の建材選定の新たな基準となっていくでしょう。
まとめ

ここまで、グラスウールとロックウールという2大断熱材について、基礎知識から違い、目的別の選び方、そして未来のトレンドまでを順にご紹介してきました。
まず、どちらも鉱物やガラスを原料にして繊維状にした「無機系の断熱材」で、空気をたくさん閉じ込める構造により、断熱性が高くなる仕組みをもっています。
資料によると、グラスウールもロックウールも、密度(10K〜40Kなど)によって熱の伝わり方に差が出ます。「密度が高い=断熱性能が高い」が基本で、高性能16Kグラスウールはロックウールとほぼ同等の熱の通しにくさ(熱伝導率)を実現しています。
ロックウールは硬くて密度がある分、中〜高音をしっかり抑えるのに向いており、音の気になるスタジオや機械室におすすめ。一方、グラスウールは柔らかく軽いため、家の壁や床の中にスッとなじむ使い方が得意です。グラスウールでもロックウールでも、きれいに隙間なく施工することが断熱性能アップの肝です。ここは熟練の技が活きるところです。
化学物質バインダーのひとつに「ホルムアルデヒド」がありますが、断熱材製造の過程で高温で固められるため、製品中の量はごくわずか。EPA(米国環境保護庁)の見解でも「ごく微量で、安全と判断されている」とされています。さらに、ノンホルムタイプの断熱材も増えており、室内空気をより安心なものにしたい現代の住宅にはぴったりです。
また、断熱材の製造・運搬・廃棄にともなう温室効果ガス排出(カーボンフットプリント)をなるべく減らす環境配慮も重要になってきています。これは、原料調達から使い終わりまでの過程でどれだけCO₂を抑えられたかを示す概念で、環境にやさしい選び方の目安になります。
住宅ならば、柔軟で施工しやすく、コスト対効果の高い高性能グラスウールを中心に検討するのをおすすめします。商業施設や工場では音や火に強いロックウールが登場する場面が増えます。
リフォームでは既存の壁構造や設備との干渉も考慮する必要があり、施工しやすいグラスウールが現実的です。
未来の断熱材は、断熱性能はもちろん、① 健康・安全性(ノンホルムなど)② 環境への配慮(カーボンフットプリントの削減)③ 施工効率(プレカットなどの工場対応)などを備えたものにも変化しつつあります。また、薄型高性能素材(真空断熱材、エアロゲルなど)への期待も高まっています。
まずはご自宅や施設の目的をしっかり整理してください(断熱性重視か、防音か、防火かなど)。
次にその目的に合った性能(数値もチェック)を明確にして、カタログや製品情報で仕様などを確認しましょう。施工業者と相談する際は、「施工の精度」「ノンホルム対応の可否」なども伝えておくと安心です。
長い目で見るなら、初期費用だけでなく「冷暖房の効率向上」も踏まえたランニングコストでの判断が重要となります。
断熱材はどれも素晴らしい性能を持つ素材です。大切なのは「その素材がどこで・どう使われるか」です。そこをしっかり見極めることで、断熱性が向上する事により、快適さ・安心・省エネまで叶えられる住まいづくりができるはずです。
これからの家づくりには、断熱材の“性能”だけでなく“使い方”も意識してみてください。
メルマガのご案内
参考リンク・関連情報はこちら
さらに詳しく知りたい方へ、信頼できる公式情報をご紹介します。
▶ グラスウール工業会(GWK)公式サイト
グラスウールの基礎、製品情報、安全性について詳しく解説。
▶ ロックウール工業会(RWAJ)公式サイト
ロックウールの用途、特性、法規対応などを網羅。
▶ 住宅性能評価・表示協会(IBEC)
断熱等性能等級や省エネ基準の根拠を知りたい方に。
▶ 環境省|断熱材とCO₂削減に関する資料
環境負荷低減と断熱性能の関係を解説。
▶ 日本建築学会(AIJ)
専門家向けの設計基準・技術指針を確認したい方に。