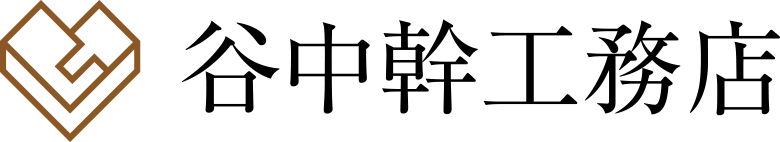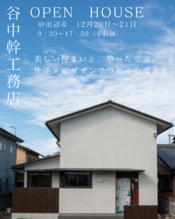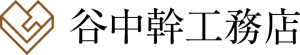庭のある暮らしがもたらす5つの豊かさ|自然・人・まちとつながる住まいのかたち

「せっかく庭があるのに、ただの“空き地”のようになっていませんか?」
日々の忙しさに追われるなかで、庭が持つ本当の価値や役割を気づかない方は少なくありません。
でも、もしその庭が、心を整える場所であり、家族の絆を育む場所であり、地域とつながる窓口でもあるとしたら——あなたの暮らしは今よりもっと、やさしく、深く、豊かに変わるはずです。
和歌山県田辺市の谷中幹工務店では、地域の気候風土や住まい方に寄り添いながら、これまで庭と住まいを設計・施工してきました。その経験から見えてきたのは、「庭のある暮らし」が持つ、計り知れない力です。
本記事では、「暮らしの中の庭時間」をテーマに、季節の移ろいを感じる日々や、家族・地域とのつながり、そして自然と共に呼吸するライフスタイルの魅力を、具体的に紹介していきます。
これを読むことで、あなたの庭が“ただのスペース”から、“生きた空間”へと変わるヒントが得られるでしょう。
庭は、家の外構ではなく、人生をもっと心地よく、美しくしてくれる舞台。さあ、一緒に“庭のある暮らし”を見つめ直してみませんか?
1. 建築と庭の一体設計がもたらす豊かさ

1-1. 住宅と庭の“連続性”を生む設計の力
住宅と庭を別々の存在としてではなく、ひとつの空間として設計する考え方が、近年の住まいづくりにおいて注目されています。建築と庭が連続性を持ってつながることで、空間に広がりと奥行きが生まれ、日々の暮らしに豊かさをもたらします。
連続性のある庭とは、たとえば室内の床と庭の地面の高さを近づけたり、素材の質感や色合いを揃えることで実現されます。視覚的な一体感があると、室内から外を眺めたときに自然と庭が生活の一部として溶け込むように感じられるのです。
この設計手法は、建築家と造園家が協力して進めることで、より高い完成度が生まれます。たとえば建物の形状や配置を庭の設計と合わせることで、自然光の取り込み方や風通しの良さも計算され、住み心地そのものが向上します。
さらに、庭の存在は単なる景観としての役割を超え、日常生活の中に“余白”や“緩やかなつながり”をつくり出します。リビングから続くウッドデッキや石畳、軒下の植栽など、小さな工夫が連続性を感じさせ、生活の質を静かに底上げしてくれるのです。
このような設計思想は、空間を単に“区切る”のではなく、“つなげる”ことを目的としています。住まいにおける庭は、部屋と部屋をつなぐ廊下のような存在にもなり得るのです。連続性のある設計によって、庭は生活に溶け込む最も身近な自然となります。
1-2. 開口部と視線の導線でつなぐ内外の風景
住宅と庭をつなぐ重要な要素のひとつに、「開口部」の設計があります。窓やガラス戸などの開口部は、単なる採光・通風のための装置ではなく、室内と庭をつなぐ“視線の通路”として機能します。この設計が適切であれば、室内から見える庭の景色が、まるで一枚の絵画のような美しさを持つのです。
開口部の位置と大きさを工夫することで、視線が自然に外へ向かい、庭の魅力を最大限に引き出すことができます。例えば、リビングの正面に大きな掃き出し窓を設け、そこから緑のボリュームが立ち上がるように植栽を配置すれば、視覚的な抜け感と奥行きが生まれ、空間に広がりを感じさせます。
視線の導線は、“何を見せて何を隠すか”という構成力にも関わってきます。例えば、隣家の視線を遮るように植栽を配置しながら、抜けのある方向には風景を切り取る。こうした意図的な視線操作が、心地よいプライベート感と開放感を両立させる鍵となります。
また、時間帯や季節によって変わる光と影の演出も、開口部の役割をより豊かにします。朝には柔らかな光が差し込み、午後には葉の影が床に落ちる。こうした日々の微細な変化が、暮らしに自然とのつながりを感じさせ、心を穏やかに整えてくれるのです。
最も理想的なのは、開口部の設計を建築段階から庭と一体で計画することです。間取りと連動した配置、外構と植栽計画のバランス、視線の向かう先の演出。それらが調和してこそ、住まいと庭が真に“つながる”空間になるのです。設計における「視線の導線」は、暮らしをデザインする上で欠かせない視点なのです。
1-3. 素材と植栽が語り合う景観づくり
庭づくりにおいて重要なのは、単に緑を植えることではなく、建築との対話を意識した“素材と植栽の調和”です。石、木材、土、金属、ガラスといった素材と、植物の色や形、高さ、質感が呼応することで、空間は一層豊かで深みのあるものになります。
たとえば、無垢材の外壁に対して、落葉樹の柔らかな葉を組み合わせることで、季節による光と影の変化を楽しむことができます。また、硬質なコンクリートに対しては、足元に下草や苔をあしらうことで、冷たさと温かみのバランスを取ることが可能です。
素材同士、あるいは植物同士の「対話」も重要です。大きな石の近くに控えめな草花を添えると、石の存在感が引き立ち、草花の可憐さも際立ちます。主張しすぎない組み合わせが、空間に余白と奥行きを生み、静かな美しさを醸し出します。
また、素材と植物の“時間の流れ”も景観づくりに影響を与えます。経年変化によって味わいが増す木材や石、成長して表情を変える植栽。時を経るごとに変化する要素を取り入れることで、「育つ風景」となり、暮らしに寄り添う存在となります。
素材と植栽の組み合わせは、空間の印象を大きく左右します。たとえば、落ち着いた色合いの石材に明るい花を添えることで、庭にメリハリが生まれ、見る人に心地よい印象を与えます。硬さと柔らかさ、高さと低さ、明暗などのバランスを意識することで、庭全体が自然にまとまり、建築とも美しく調和します。
1-4. 建築のディテールと調和する緑の使い方
建築のディテールとは、外壁の素材感や窓のフレーム、庇の出幅、屋根の形状など、細部にわたる設計要素を指します。これらの細やかな設計と調和するように植栽を配置することで、住宅全体が美しくまとまり、庭もその延長線上にある空間として自然に溶け込みます。
たとえば、シンプルで直線的なモダン住宅には、繊細な葉を持つ植栽やすっきりとした樹形の樹木がよく合います。逆に、和風建築や自然素材を用いた住まいには、雑木林を思わせるような野趣あふれる植栽を選ぶことで、建築と庭の雰囲気が共鳴します。
ディテールに呼応する緑の使い方として、窓辺の足元にさりげなく下草を植えたり、屋根のラインに沿うように樹木を配置したりといった工夫があります。こうした繊細な調整が、空間全体のバランスを整え、見る人の視線を自然に誘導する効果を持ちます。
また、建築の素材や色調に合わせた植栽選びも重要です。例えば、グレー系のタイル外壁にはシルバーリーフ系の植物を、木材を多用した外観には暖かみのある紅葉樹を取り入れるなど、色彩の調和を意識することで、景観に一体感が生まれます。
建築と緑が調和する庭は、住まい全体の印象を格段に高めてくれます。無理に主張するのではなく、背景として静かに佇む緑の存在は、空間に奥行きと豊かさを加え、暮らす人の感性に寄り添う「余白」を与えてくれるのです。
1-5. 設計プロセスで“庭”をどう組み込むか
住宅設計において庭を後から付け加えるのではなく、初期段階から「庭を含めた空間設計」を考えることが、より完成度の高い住まいをつくる鍵となります。建物の配置、窓の位置、動線計画といった基本設計の時点で、庭の役割や位置づけを明確にしておくことが重要です。
設計プロセスの初期から庭を計画に含めることで、室内からの視線の抜け、プライバシー確保、採光・通風、さらには生活動線までもが自然に整います。たとえばダイニングの前に緑を配置すれば、食事の時間がより豊かになり、リビングからの視界に奥行きをもたせれば、空間全体が開放的に感じられます。
また、建築と庭の関係性を設計段階で整理しておくことは、無駄のないコスト設計にもつながります。あらかじめ配置や素材、植栽の方向性が定まっていれば、施工時に大幅な変更や調整が不要となり、結果としてトータルの品質と効率が向上します。
このような設計方法を可能にするには、建築家と造園家、そして施主が密にコミュニケーションをとることが欠かせません。三者がビジョンを共有し、敷地の特性やライフスタイルを元に庭の位置づけを丁寧に定義していくことで、暮らしと調和する庭が生まれます。
設計プロセスに庭を組み込むとは、単に「庭を設ける」という行為ではありません。それは、住まいに流れる時間や風、光、音を意識し、それらと共に暮らすための“余白”を設計することです。そうして初めて、庭は単なる外構ではなく、「暮らしの一部」として機能する空間になるのです。
2. 地域・環境とつながる庭の思想

2-1. 里山の原風景を取り込む庭づくり
現代の住宅地においても、心の奥に残る「里山の原風景」を取り入れた庭づくりは、多くの人々に深い安らぎをもたらします。雑木林のような自然な植生や、素朴な石や土の素材感を生かすことで、人工的な空間の中に“どこか懐かしい”情景を呼び起こすことができます。
里山風の庭づくりでは、整いすぎた美しさよりも、自然の不均衡や揺らぎを大切にします。たとえば、樹木の高さを揃えずに高低差をつけたり、落ち葉が地面に残るように管理することで、自然本来の風合いが生まれます。手を加えすぎない「余白」が、住まいに深みと趣を加えるのです。
このような庭は、単なる景観ではなく「体験の場」としての価値も持っています。小鳥のさえずり、風に揺れる葉音、足元に咲く小さな野草など、五感を通じて自然とのつながりを感じることができます。果実の収穫なども私も楽しみにしている事です。そう、庭に出るたびに、新しい発見と出会える楽しさがあります。
さらに、里山の風景を模した庭は、周囲の街並みにも穏やかな影響を与えます。塀で完全に囲わず、ゆるやかに“まちにひらく”ような設計にすることで、地域の景観と調和し、通行人や隣人にも心地よい印象を与えることができます。
このような庭づくりには、短期間での完成を求めるのではなく、長い年月をかけて育てていくという発想が必要です。時を重ねるほどに味わいが増し、住まいと共に成長していく。そうした庭こそが、私たちの暮らしに本当の意味での“自然”を取り戻してくれるのです。
2-2. 地域植生と在来植物の美しさを活かす
庭づくりにおいて、地域に根ざした植生や在来植物を活用することは、環境への配慮とともに、景観の自然な美しさを引き出すうえで非常に有効です。その土地で昔から育っている植物は、気候や風土に適応しており、無理なく育てやすく、手入れの負担も少ないというメリットがあります。
在来植物の魅力は、見た目の美しさだけでなく、その土地特有の風景や記憶を呼び起こす点にもあります。例えば、ヤマボウシやアオダモといった樹種は、自然な枝ぶりとやさしい葉の動きが特徴で、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。地域の原風景を感じさせる存在です。
また、在来種の植栽は、昆虫や鳥などの生態系を支える役割も果たします。外来種では生み出せない自然の循環がそこにはあり、小さな庭の中にも豊かな命の営みが感じられるようになります。これにより、庭が単なる鑑賞の場ではなく、「いのちが交差する場所」へと変わっていきます。
在来植物は見慣れた存在であるがゆえに、時に“地味”と捉えられがちですが、だからこそ、他の要素と調和しやすく、建築とも自然につながります。過度に装飾的な植物を選ぶのではなく、さりげない美しさを持つ植物を丁寧に配置することで、静かで上質な庭が生まれます。
地域植生や在来植物を活かした庭は、見た目の美しさを超えて、土地と人、暮らしと自然をつなぐ大切な“接点”となります。その土地に根ざした緑は、暮らしに穏やかなリズムと風景をもたらし、庭に深い意味と物語を宿すのです。
2-3. 既存樹木を活かすという選択肢
家づくりや庭づくりの際、多くの人が更地からスタートすることを前提に考えますが、実は敷地内に既存の樹木がある場合、それを活かすという選択肢には大きな価値があります。すでに根を張り、地域の気候に馴染んでいる木は、その土地にしかない“時間の記憶”を宿しているのです。
既存樹木を残すことには、多くの利点があります。まず第一に、植え替えや新たな成長を待たずとも、庭に豊かな緑陰や景観がすぐに生まれる点です。また、風を和らげたり、夏の強い日差しを遮ったりと、自然の力を借りた快適な住環境づくりにもつながります。
既存の木を中心に据えて設計を進めると、庭の配置や建物の開口部、動線の計画にも新しい発想が生まれます。たとえば、大樹を中庭の主役に据えることで、室内からの眺めに奥行きが加わり、四季折々の表情を日常的に楽しむことができます。
一方で、既存樹木を残すには、根の位置や健康状態、将来的な成長を考慮した慎重な計画が必要です。建築や外構と干渉しないように配置を工夫し、場合によっては専門家の診断や移植も視野に入れることで、安全かつ美しい景観を維持することができます。
既存の木を活かすという行為は、自然を尊重する姿勢であると同時に、そこに流れてきた時間への敬意でもあります。木と共に暮らすことは、過去と現在、そして未来を緩やかにつなげること。新築やリフォームの際には、目の前の一本の木に、もう一度目を向けてみる価値があるのです。
2-4. 庭を“まちにひらく”という発想
住宅の庭というと、プライベートな空間として囲い込み、外から見えないようにする設計が一般的でした。しかし近年では、庭を「まちにひらく」という新しい発想が注目されています。これは、庭を通じて地域と緩やにつながることで、街の風景や人の流れに貢献するという考え方です。
完全に開放するのではなく、あえて視線の通り道をつくったり、低めの植栽で境界をゆるやかに仕切ることで、通りがかりの人にも季節の変化や緑の心地よさを感じてもらうことができます。これにより、住宅の庭が個人だけのものではなく、まちの一部として機能し始めます。
このような設計は、都市の中に“やわらかな境界”を生み出し、まち全体に落ち着きと潤いをもたらします。小さな緑地が連続することで、まちに「緑のネットワーク」が生まれ、街路樹や公園とは違った身近な自然としての役割を果たします。
また、まちにひらかれた庭は、人と人のつながりを生むきっかけにもなります。道端で花の話を交わしたり、季節の挨拶を交わしたりと、ちょっとしたコミュニケーションが生まれやすくなるのです。庭が、無言のうちに地域の絆を育む存在になっていきます。
庭をまちにひらくという選択は、景観としての美しさだけでなく、地域社会との関係性や街の空気感をも変えていきます。人と人、自然とまちがつながるこの思想は、これからの時代にふさわしい「庭のかたち」と言えるでしょう。
2-5. 景観の一部として庭を設計する責任
庭は、自分のためだけの空間ではありません。家の前に広がるその一角は、道を行き交う人の目にふれる「まちの風景」のひとつ。だからこそ、庭をどんなふうに作るかには、ちょっとした責任も伴います。
たとえば、背の高い塀でしっかり囲んでしまえば、安心感はあるけれど、街から見れば少し閉ざされた印象に。反対に、緑や低い植栽でゆるやかに仕切る庭は、まちに自然なつながりを感じさせ、優しい雰囲気を生み出してくれます。
自分の家のまわりに、ちょっとした草木があるだけで、通りがかる人の気持ちが和らぐこともあります。「ここを通ると気持ちいいな」と思ってもらえる庭は、地域全体の空気をあたたかくしてくれる存在になるのです。
春には花が咲き、夏には木陰ができ、秋には色づき、冬には枝の姿が美しい。そんな四季のうつろいをさりげなく伝えてくれる庭は、まちの中に季節のリズムを届ける「ちいさな自然」と言えるでしょう。
庭は家の一部でありながら、まちの一部でもあります。そのことを少しだけ意識して庭をつくると、暮らしの心地よさも、地域とのつながりも、ぐっと深まります。庭づくりは、自分のためでもあり、まちの風景へのやさしい贈り物でもあるのです。
3. 暮らしの中の「庭時間」を楽しむ

3-1. 見る・歩く・感じる庭の時間
庭は、ただ眺めるだけの場所ではありません。窓越しに見る景色としても、朝の散歩コースとしても、ふと立ち止まって風を感じる場所としても、暮らしの中に「庭の時間」はそっと存在しています。日常の中にある、ちいさな自然とのふれあい。それこそが、庭のいちばんの魅力かもしれません。
たとえば、朝起きてカーテンを開けたとき、庭に朝日が差し込んでいるのを見るだけで、少し心が整います。晴れた日は、素足のまま外に出て一周する。葉の揺れや土の香り、空の高さを肌で感じると、心と体が自然と軽くなっていくのを実感するはずです。
こうした「歩いて感じる庭」は、必ずしも広いスペースでなくてもかまいません。ちょっとした小道や、飛び石、木陰のベンチがあるだけで、庭の中に小さな旅が生まれます。庭の中を少し歩くだけで、気持ちがリセットされる——そんな時間があると、暮らしはぐっと豊かになります。
また、季節の移ろいを目で感じられるのも庭ならではの魅力です。春には新芽、夏には青葉、秋には紅葉、冬には枝の陰影。季節を感じながら生活できる環境は、自然と気持ちに余裕を生み、日々をていねいに過ごすきっかけになります。
庭の時間は、何かをするための時間ではなく、ただそこに“居る”だけでも価値があります。五感で感じる自然のリズムが、知らず知らずのうちに心を整えてくれるのです。忙しい毎日の中に、ふと庭に出て深呼吸する——そんな小さなひとときが、暮らしの質を静かに高めてくれます。
3-2. 季節の変化を暮らしに取り込む
庭がある暮らしのいちばんの楽しみは、なんといっても季節の変化を身近に感じられることです。室内にいながらにして、春の芽吹き、夏の緑陰、秋の色づき、冬の静けさ。四季が少しずつ移り変わっていく様子を、庭は日々の景色の中に映し出してくれます。
朝、ふと窓の外を見ると、昨日まではなかった小さな花が咲いている。そんな小さな変化に気づくことは、心にゆとりがある証かもしれません。季節の移ろいに気づく庭があることで、日々の暮らしが少しずつ丁寧になっていきます。
また、庭の植物は、季節の移ろいを“行事”として感じさせてくれる存在でもあります。春には芽吹きのお祝い、夏は木陰での涼、秋は落ち葉を集めて遊び、冬は剪定と春支度。暮らしの中に、自然のカレンダーがそっと組み込まれていくのです。
子どもたちにとっても、季節の変化を肌で感じられる庭は、大切な学びの場になります。草花の成長や虫の姿、風の匂い。自然の中で体験することは、教科書には載っていない、心に残る「暮らしの知恵」として積み重なっていきます。
庭に出るたびに変化があるというのは、それだけで贅沢なこと。何気ない日常の中に、小さな感動や発見があることで、暮らしはもっと味わい深くなります。季節とともに生きるということの豊かさを、庭が静かに教えてくれるのです。
3-3. 手を入れるほど愛着が深まる日々
庭の楽しみ方は人それぞれですが、自分の手で手入れをする時間は、庭との距離をぐっと縮めてくれる大切なひとときです。草を抜いたり、花がらを摘んだり、落ち葉を掃いたり。そんな小さな作業の積み重ねが、いつの間にか庭に対する愛着を育てていきます。
はじめは義務のように感じていた作業も、続けているうちに不思議と気持ちが落ち着いてくるものです。土に触れる、葉に触れる、風を感じる——そんな五感の刺激が、心と身体のバランスを整えてくれる癒しの時間へと変わっていきます。
自分で手を入れることで、庭の変化に敏感になります。「この木はちょっと元気がないな」「今年は花付きがいいな」と、植物のちょっとした表情に気づくようになると、庭がまるで家族の一員のように思えてくるから不思議です。
手入れを通じて、庭の“成長”にも関わることができます。剪定の仕方ひとつで枝ぶりが変わり、花の咲き方が変わる。毎年違う表情を見せてくれる庭は、自分とともに歳月を重ねていく存在になります。
庭は完成されたものではなく、「育てていく空間」です。少しずつ自分の手で整えていくことで、その庭は世界にひとつだけの場所になっていきます。手をかけるほどに深まる愛着は、何ものにも代えがたい、暮らしの宝物になるでしょう。
3-4. 家族や来客との自然な交流の場
庭は、自分ひとりで楽しむだけでなく、家族や友人と過ごす時間を豊かにする空間でもあります。とくに屋外という開放感のある場だからこそ、肩の力を抜いて自然に会話が生まれるのも魅力のひとつです。
休日の朝、庭に椅子とテーブルを出して家族で朝食をとる。春にはお花見、夏には夕涼み、秋には落ち葉拾い、冬には温かい飲み物を片手に。庭があれば、どんな季節でも自然と人が集まり、心地よい時間が流れはじめます。
来客を庭で迎えるというのも、日常にちょっとした特別感を与えてくれます。玄関先ではなく、庭の緑に囲まれた空間で過ごす時間は、会話をより和やかにし、訪れる人の記憶にも心地よく残ります。
また、子どもたちにとっても庭は遊び場であり、探検の場でもあります。虫を見つけたり、木の実を拾ったり、草花を摘んだり。自然とふれあいながら生まれる遊びは、スクリーンの中では得られない、かけがえのない体験です。
庭があるだけで、人と人との距離が自然と近づく。無理に会話をしなくても、風に揺れる葉を眺めながら一緒に過ごすだけで、そこには心地よい時間が流れます。庭は、暮らしの中に「つながり」を生み出す、やさしい舞台なのです。
3-5. 自然と共に呼吸する暮らしのかたち
忙しい毎日の中で、ふと深呼吸したくなる瞬間はありませんか?そんなとき、庭に出て風を感じるだけで、不思議と心が軽くなることがあります。自然のリズムに身をゆだねることで、私たちは本来の呼吸を取り戻すのかもしれません。
庭のある暮らしは、自然とともに「暮らしのテンポ」も整えてくれます。朝の光で目覚め、季節の花に目をとめ、風の音を耳にする。そんなふうに、一日の流れや一年の巡りを、庭がそっと教えてくれます。
エアコンや照明に頼らず、緑の力で涼やかに過ごす夏の日。落ち葉を掃きながら冬支度を整える秋の朝。自然と寄り添う暮らしは、環境にも体にもやさしく、丁寧な暮らし方を自然と身につけるきっかけになります。
「暮らしに庭がある」のではなく、「庭とともに暮らしている」。そんな意識で日々を過ごすことで、心の中にもゆとりが生まれます。自然と調和した生活は、気持ちに余白をつくり、人生をより豊かなものにしてくれるのです。
庭とともにある暮らしは、決して特別なものではありません。日常の延長線上にある、ちいさな自然との共存です。そんな暮らしの中にこそ、本当の豊かさや心地よさがあるのだと、庭は静かに教えてくれるのです。
まとめ

庭はまた、人との関係性を自然に育む場所でもあります。家族が集まって食事をしたり、子どもが遊んだり、来客とお茶を楽しんだり——そうした時間の中で、庭は静かに人と人とをつなぎ、心と心がほどける場を提供してくれます。自然に囲まれた空間では、言葉にしなくても通じる安心感があります。
このような「ひらかれた庭」は、時にまちとの接点にもなります。通りすがりに花を眺めたり、季節の移ろいを感じたりする庭は、そこに住む人だけでなく、地域全体の空気をやわらかくしてくれます。高い塀で閉ざすのではなく、視線をやさしく受け止めるような庭のあり方が、まちに心地よい景観をもたらすのです。
庭づくりにおいて大切なのは、「完成」を目指すのではなく、「育てていく」という視点です。植物は日々成長し、庭の表情は常に変化していきます。手を入れれば入れるほど、庭との対話が生まれ、自分自身の暮らしにも愛着と豊かさが深まっていきます。
もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。少しずつ、自分のペースで関わることが大切です。忙しい日は水やりだけ。余裕のある日は草取りや剪定に少し時間をかけてみる。そんな風に、庭との付き合い方もまた、暮らしのリズムの一部となっていきます。
本記事を通して、庭という存在が私たちの暮らしにもたらしてくれる、さまざまな豊かさや可能性を感じていただけたのではないでしょうか。自然と建築が調和し、地域とつながり、日常にやさしい時間が流れる——そんな庭のある暮らしは、これからの住まいづくりにおいて、より大切な価値になると確信しています。
都市緑化や緑化技術に関する知識を深めたい方は、公益財団法人都市緑化機構のサイトをご覧ください。
緑豊かなまちづくりや庭のデザインに役立つ事例・研究情報が多数掲載されています。