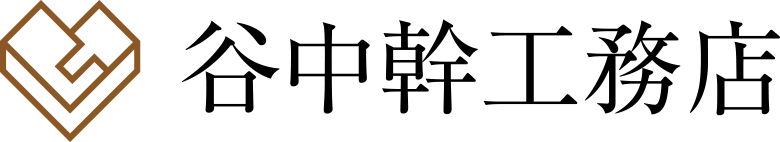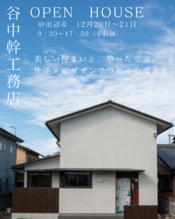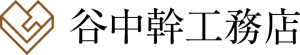収納が使いにくい掃除しにくい理由は間取りにあった?プロが教える整う住まいのつくり方

目次
毎日の片付けと掃除、気づけば“やらなきゃ”の連続で、ちょっとしたストレスになっていませんか?
「せっかく収納を増やしたのに、なんだか片付かない」「掃除が億劫で後回しにしがち」──そんな声は多くのご家庭で聞かれます。
けれど実は、それらの悩みの多くは“住まいの設計”の段階で防げるということをご存じでしょうか?
数多くの住まいづくりに携わる中で、「収納と掃除のしやすさ」こそが、暮らしの快適さを左右する重要な要素であることを確信しています。
本記事では、そんな住まいの“暮らしやすさ”を高めるために、
▶収納は使いやすく、掃除はついでにできるように
▶造作家具や動線計画で手間を減らす
▶家族全員が自然とキレイを保てる仕組みを設計する
など、家づくりのプロ視点で実践的なアイデアを凝縮してお届けしています。
読んだその日から使える視点ばかりなので、これから家を建てる方はもちろん、今のお住まいを整えたい方にも役立ちます。
あなたの暮らしを、ただの“箱”ではなく、自然と片付け・掃除が続く住まいへと進化させませんか?
そんなヒントがきっと、このページに見つかります。
この記事から得られる5つの結論
収納は「使いやすさ」が最優先。
使用頻度や動線に合わせて配置し、しまいやすく取り出しやすい設計が暮らしを整える鍵になります。
掃除は「ついでにできる」ことが継続のコツ。
家具配置や段差の工夫、掃除道具の定位置化で、自然と掃除を習慣に取り入れやすくなります。
高断熱・高気密住宅と計画的な換気が清潔の基盤。
カビやホコリの発生を抑え、健康的で快適な住環境をつくるために欠かせない要素です。
掃除と収納は家族全員で“自分ごと”として共有。
誰か一人に負担が偏らず、暮らし全体の快適さが保たれます。
家づくりの段階で「掃除しやすさ」を設計に。
掃除や整頓が自然に続く仕組みを住まいに組み込むことで、無理なくキレイが続く家が実現できます。
1. 収納計画の基本

1-1. 家族構成に合わせた収納設計
収納計画を立てる際に最も重要なポイントのひとつが、家族構成に応じた収納の量と種類を見極めることです。たとえば、夫婦ふたりの生活と、子どもが複数いる家庭とでは、必要とされる収納のスタイルも容量もまったく異なります。特に成長期の子どもがいる家庭では、学用品や衣類、おもちゃなど、短期間でモノの種類と量が大きく変化するため、それを見越した柔軟な設計が求められます。
また、収納の配置や使いやすさも家族全員がストレスなく暮らすために大切です。小さな子どもがいる場合は、自分で出し入れできる高さに収納を設けたり、危険なものは上部に配置したりと、年齢や行動パターンを考慮する必要があります。一方、高齢者と同居している家庭では、無理な姿勢を強いる収納は避けるべきで、出し入れが簡単な引き出しやスライド棚が理想的です。
家族構成の変化に対応できる「可変性」も重要な視点です。たとえば、可動式の棚や仕切りを使えば、子どもの成長やライフスタイルの変化にあわせて収納スペースを再構成することができます。特にクローゼット内やパントリー、洗面収納などは、こうした調整がしやすい仕様にしておくと、将来的にも使い勝手が良くなります。
「誰が、どこで、何を使うか」を家族で共有することも、収納計画を成功させるコツのひとつです。家族全員がどこに何があるかを把握していれば、無駄な探し物が減り、片付けの負担も軽減されます。特に、共有スペースに置くべきものと個人の私物を明確に分けることで、整理整頓がスムーズになります。
最後に、収納計画を立てる際は、将来のライフステージも見据えることが大切です。子どもが独立した後や、自宅で仕事を始めるようなライフスタイルの変化にも対応できるようにしておくことで、住まいに対する満足度が長く続くでしょう。収納は単なる「モノをしまう場所」ではなく、暮らしの質を左右する大きな要素なのです。
1-2. 使用頻度に応じた収納の分類
効率的な収納を実現するためには、使用頻度に応じてモノを分類し、それぞれに適した場所へ収納することが基本となります。よく使うものを奥にしまい込んでしまうと、日々の生活にストレスが生まれがちです。たとえば、毎日使う調理器具や調味料はキッチンの手の届く位置に、逆に年に数回しか使わない季節用品は納戸やクローゼットの上部、家具の下部スペースなど、普段の生活動線から少し離れた場所にまとめることで、限られた空間を有効活用できます。
この「頻度別収納」は、家全体の収納効率を飛躍的に高めるだけでなく、片付けのしやすさにも直結します。たとえば、掃除道具を日常的に使う場所の近くに置いておけば、ちょっとした汚れにすぐ対応できるなど、行動と収納がリンクした仕組みを作ることで、自然と片付いた暮らしが維持しやすくなります。
また、家族全員が使うものと、個人専用のものを分ける際にも、使用頻度の視点は重要です。共有の収納には日々の生活に不可欠なアイテムを集約し、個人の収納には趣味や特定の活動で使うアイテムを配置することで、それぞれのライフスタイルにフィットした収納が可能になります。この分け方は、家族間の収納トラブルを防ぐ効果もあります。
使用頻度に応じた分類は、時間の経過とともに見直すことも大切です。生活スタイルや季節の変化によって、よく使うもの・使わなくなったものが変わるため、収納もそれに合わせて調整する必要があります。定期的な見直しによって「使いやすさ」を維持し、不要なモノを溜め込まない習慣づけにもつながります。
最後に、使用頻度の分類を視覚的にサポートする工夫として、ラベルや透明ケースの活用が挙げられます。よく使うものは見える収納にしてアクセスしやすく、使用頻度が低いものはカテゴリごとにまとめて見えない収納へ。視覚と行動を一致させた収納設計によって、自然と片付けやすく、探し物も減る住まいになります。
1-3. 動線と収納の関係性
家の中で「動線」を意識することは、快適な暮らしのために欠かせないポイントです。動線とは日常の行動の流れを指し、たとえば「帰宅→手洗い→着替え→リビングでくつろぐ」といった一連の動きに沿った配置ができているかが重要になります。この動線上に必要な収納が適切に配置されていれば、モノの出し入れがスムーズになり、自然と片付けも楽になります。
動線を無視した収納計画では、モノの使用場所と収納場所が離れてしまい、毎回余計な動きを強いられることになります。たとえば、玄関で使うマスクや鍵をキッチンに収納してしまえば、出かけるたびに家の中を行ったり来たりしなければなりません。これでは、日常のちょっとした行動がストレスになり、片付けも億劫になってしまいます。
よくある失敗例として、収納スペースはたっぷりあるのに「使いにくい」と感じてしまうケースがあります。これは、収納の容量よりも「動線に合っていない場所」にあることが原因のひとつです。特に生活動線の中心となる場所——玄関まわり、洗面所、キッチン、リビングなど——に用途ごとに整理された収納があると、日々の行動が非常にスムーズになります。
また、動線に沿った収納は掃除のしやすさにも直結します。必要なものが必要な場所にあることで、モノが床やテーブルに出しっぱなしになることが減り、掃除機やモップをかけやすくなるのです。動線上に「しまう→掃除する」という流れを意識した収納配置を取り入れることで、無理なく整理整頓された空間を保つことができます。
動線を意識した収納は、家族全員が「片付けやすい」住まいを実現する鍵にもなります。収納の場所が明確で、行動に沿った位置にあることで、子どもでも自然と片付けの習慣が身につきやすくなります。家事の負担も減り、誰にとっても使いやすい家にすることができます。収納は単なる空間ではなく、暮らしをサポートする「導線設計」(人の動きを意図的に導く仕組み)の一部であるという視点を持つことが、より快適な暮らしへとつながります。
1-4. 見せる収納 vs 隠す収納
収納を考えるうえで重要な選択のひとつが、「見せる収納」にするか「隠す収納」にするかという点です。どちらにもメリットとデメリットがあり、住まいのテイストや家族のライフスタイルによって最適なバランスが変わります。インテリア性を重視する方にとっては、見せる収納は空間を彩る手段にもなりますが、使い方を誤るとごちゃついた印象になりかねません。
見せる収納の利点は、「使いたいものがすぐに手に取れる」「モノの存在を忘れずに済む」「空間のアクセントになる」などが挙げられます。オープンシェルフや壁面ラックを利用すれば、雑貨や書籍、観葉植物などをディスプレイのように飾ることができます。一方で、常に整頓された状態を保つ必要があり、片付けが苦手な方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。
対して隠す収納は、見た目のすっきり感と掃除のしやすさが大きな魅力です。引き出しや扉付きの収納を活用すれば、モノをしまった状態で空間が整って見え、生活感を出さずに済みます。来客が多い家庭や、忙しくて細かな整理が難しい方には特に向いているスタイルといえるでしょう。ただし、「何をどこにしまったか」が分かりにくくなることがあるため、ラベリングや仕分けが重要になります。
効果的な収納を目指すなら、「見せる」「隠す」を単体で考えるのではなく、空間の用途やモノの種類によって組み合わせることが理想的です。たとえば、日常的によく使うアイテムは見せる収納に、ストックや季節用品は隠す収納にといった具合に、目的別で使い分けると、暮らしにメリハリが生まれます。
最終的には、家族全員が使いやすく、維持しやすい方法を選ぶことが何より大切です。見た目の美しさだけでなく、「無理なく続けられるか」という視点を持つことで、収納はより機能的で満足度の高いものになります。収納計画の段階で、「どこを見せて」「どこを隠すか」を考えることで、空間全体に一貫性が生まれ、暮らしやすさとデザイン性の両立が可能になります。
1-5. 収納量の目安とその計算方法
適切な収納計画を立てるためには、まず「どれくらいの収納が必要なのか」を具体的に把握することが大切です。収納量の目安を知らずに家を設計してしまうと、後から「収納が足りない」「使いづらい」といった問題が発生しやすくなります。実は、収納スペースの広さには一定の基準があり、一般的には住宅全体の延べ床面積の10〜15%が理想とされています。
たとえば、延べ床面積が100㎡の家であれば、10〜15㎡が収納として確保されるべきということになります。ただし、この数字はあくまで「合計」であり、収納が一箇所に集中していても使い勝手が悪くなるため、部屋ごとや動線に沿って分散配置することが前提です。収納のバランスと配置が整って初めて、この基準が生きてきます。
また、収納するモノの種類や家族構成によっても必要な収納量は大きく変わります。衣類や本が多い家庭、趣味の道具がかさばる家庭などは、そのライフスタイルに応じて上記の基準以上の収納を確保する必要があります。一方で、モノを持たないミニマルな暮らしを目指す家庭であれば、やや少なめでも快適に過ごせることもあります。
計画をする際は、実際に収納する予定のモノをジャンルごとにリスト化し、それぞれに必要なスペースを具体的に見積もる方法が有効です。たとえば衣類や靴などであれば、「長さ」で考えると非常に分かりやすくなります。家族4人であれば、おおよそ5.5メートル分のハンガーパイプの長さが必要といった具合に、数値で把握することで計画性が高まります。このように見える化することで、過不足のない収納計画が立てやすくなり、家づくりに安心感が生まれます。
最後に意識したいのが、「モノを持ちすぎない」という視点です。収納を増やせば増やすほど、不要なモノもつい溜め込んでしまいがちです。だからこそ、収納計画と合わせて定期的な断捨離を習慣化することが、住まいの快適さを保つためには欠かせません。余裕のある収納とは、スペースを増やすことではなく、必要なモノだけを持つことで自然と生まれるもの。これが結果として、見た目のすっきり感や、心のゆとりにもつながっていきます。
2. 掃除しやすい住まいづくり

2-1. 毎日の掃除がラクになる住まいの習慣設計
掃除を無理なく続けるためには、道具や時間の工夫だけでなく、「習慣にしやすい住まいの構造」も大きく関わってきます。毎日の掃除が負担に感じるのは、掃除のしづらい構造や、ものが散らかりやすい動線によるものが多いのです。だからこそ、掃除という行動を暮らしに組み込みやすくするよう、住まいの中に自然な習慣設計を施すことが重要になります。
習慣化しやすい掃除には、まず「すぐに掃除できる状態」が欠かせません。たとえば、リビングや洗面所など、よく使う場所には掃除道具を目立たない位置に置いておくことで、気になった時にサッと取り出して対応できます。わざわざ物置まで取りに行く必要があると、それだけでハードルが上がるため、掃除の「ついで」ができる動線があると、無理なく続けられます。
また、「片付けと掃除をセットにする」意識も重要です。テーブルの上を片付けたら、ついでに拭き掃除。脱いだ服をしまうついでに、床もサッとモップがけ。動作と動作をつなげることで、掃除だけを特別な作業にせず、日常の一部として取り入れることができます。こうした行動を習慣化するには、行動動線に沿った収納や道具の配置が鍵になります。
家族全員で掃除の習慣を共有するためには、「わかりやすいルール」と「役割の見える化」が効果的です。たとえば曜日ごとに掃除場所を決めたり、子どもにもできる範囲の掃除を用意したりすると、家族全員が参加しやすくなります。住まいの構造に沿って、誰でも迷わず掃除できる工夫をすることで、掃除が「自分ごと」として根づいていきます。
掃除のしやすさは、家そのものの構造だけでなく、日々の行動をどう設計するかに大きく左右されます。「気がついたときにすぐ動ける」「動線に沿ってムダがない」「家族みんなで自然と続けられる」——こうした仕組みを住まいの中に作ることで、特別な掃除日を設けなくても、いつでもきれいな状態を保てる暮らしが実現します。掃除を「イベント」から「習慣」へ変える住まいづくりが、快適な毎日の鍵なのです。
2-2. 家具配置と掃除のしやすさ
家具の配置は、空間の見た目や使い勝手だけでなく、掃除のしやすさにも大きな影響を与えます。たとえば、家具と壁のすき間が狭すぎると掃除機が入らず、ホコリがたまりやすくなります。また、床にモノが多い状態では、掃除のたびに持ち上げたり移動したりする手間が増え、自然と掃除が後回しになってしまいます。掃除しやすい家具の配置とは、掃除の動作を妨げない「余白のある設計」といえます。
家具選びの段階でも、掃除のしやすさを意識すると日々の手間が軽減されます。たとえば、脚付きのソファやベッドを選ぶことで、下に掃除機やロボット掃除機を通しやすくなります。逆に、低くて床にベタ付きする家具は、ホコリがたまりやすい場所となりがちです。床から浮いた家具が多いほど、掃除が自然にしやすくなります。
動線を考慮した家具配置も重要なポイントです。人の通り道が狭いと、移動するたびに家具にぶつかってモノがずれたり、掃除機が引っかかったりするなど、ちょっとしたストレスが積み重なります。掃除のしやすい動線とは、「回遊性」と「視界の抜け」があるレイアウトです。家具が壁に寄せられていて、中央が開けているだけでも掃除効率は大きく変わります。
また、家具を壁にぴったりと付けすぎないことも、ホコリ対策には有効です。ほんの数センチのすき間があるだけで、ハンディモップやノズル付き掃除機を差し込んで、ホコリを溜め込まない工夫が可能になります。密着させすぎた家具は、一見スッキリしていても、裏でホコリが蓄積されるリスクを抱えることになるため注意が必要です。
最終的に大切なのは、家具を「動かしやすい」「下にアクセスしやすい」「ホコリが溜まりにくい」状態に保つことです。そのためには、家具の重さや材質も考慮に入れると良いでしょう。キャスター付きの家具や、軽量で持ち上げやすいアイテムを選ぶことで、掃除のハードルがぐっと下がります。見た目や機能だけでなく、掃除との相性を意識することで、住まい全体の清潔感が保たれやすくなります。
2-3. 段差・隙間の工夫でほこり対策
家の中の「段差」や「ちょっとした隙間」は、見落とされがちですが、実はホコリがたまりやすい原因のひとつです。特に掃除機が入りにくいすき間や段差の出入り口は、ホコリが溜まるだけでなく、掃除のたびに手間がかかります。こうした場所をいかに減らすか、または掃除しやすくするかが、清潔を保つ住まいづくりには重要なポイントとなります。
たとえば、部屋ごとの床の高さに段差があると、ゴミが引っかかって止まりやすく、掃除機やモップの動きがスムーズにいかなくなります。近年はバリアフリー設計が主流ですが、それは高齢者や子どもに優しいだけでなく、掃除のしやすさという面でも非常に合理的です。可能な限りフラットな床にすることが、日々の掃除をラクにするコツです。
隙間対策として有効なのが、すき間を「なくす」か「掃除しやすくする」かのどちらかに割り切ることです。家具と壁の間に中途半端なすき間があると、ホコリがたまっても掃除道具が入らず、そのまま放置されがちになります。こうした場所は、造作家具などでぴったりと塞いでしまうか、逆にすき間をあえて広く取り、掃除がしやすい構造にするのがベストです。
配線まわりもほこりが集まりやすい場所です。テレビボードやデスク周辺など、配線が露出していると、ホコリが絡まりやすく掃除の手間が増えます。これを防ぐには、配線をまとめる・隠す・浮かせるなどの工夫が効果的です。コンセント位置を高めに設けたり、配線ダクトを組み込んだりすることで、掃除機がスムーズに通る空間が生まれます。
最後に、掃除ロボットに対応した設計も現代の住まいづくりでは欠かせません。床に段差がない、すき間が5〜10cmある、コード類が整理されているなどの条件が整っていれば、ロボット掃除機が家じゅうを自動できれいに保ってくれます。掃除を手放すことができる住まいにするためにも、「段差」と「すき間」は積極的にデザインしていくべき要素なのです。
2-4. 換気計画とカビ・汚れ対策
高気密・高断熱住宅は、室内の温度を安定させ、外気の影響を受けにくい快適な住まいを実現できる点で非常に優れています。しかし、その性能を十分に活かすには、適切な換気計画が不可欠です。高気密であるがゆえに、空気の出入りが計画通りに行われないと、湿気や汚れが室内に滞留しやすくなり、カビや結露の原因になることもあります。つまり、高性能な住宅だからこそ、換気を“設計の一部”として考えることが、清潔な住環境を保つためのカギとなるのです。
換気計画において大切なのは、家の中に空気の流れを意図的に作ることです。そしてそのためには、高気密な住宅であることが前提になります。気密性が高ければ空気の出入りをコントロールしやすく、24時間換気などの機械換気も効果的に機能します。逆に気密性が低い家では、空気が想定外の隙間から出入りしてしまい、十分な換気が行われにくくなるため、せっかくの換気設備が十分に力を発揮できません。つまり、換気性能を最大限に活かすには、高気密住宅が有利なのです。
自然換気だけでなく、機械換気システム(24時間換気)の導入も今や欠かせない要素です。常に空気をゆるやかに循環させることで、空気中の湿気やハウスダスト、生活臭などの滞留を防ぎ、清潔な空気環境を保てます。定期的なフィルター清掃は必要ですが、空気環境を整えるという点では、掃除の回数を減らす効果も期待できます。
カビ対策として最も効果的なのは、住宅の断熱性と気密性を高めることです。高断熱・高気密の家は、外気との温度差が少ないため室内の結露が起こりにくく、カビの発生原因を大きく抑えることができます。特に収納内部や北側の部屋など、温度差が生じやすい場所でも、断熱がしっかりしていれば湿気がこもらず、カビが生えにくい環境を保てます。換気や除湿に頼りすぎるのではなく、住宅そのものの性能でカビを予防するという発想が重要です。
最後に意識したいのは、窓の配置や採光の工夫です。日光が入りやすい環境は、湿気を飛ばし空間を乾燥させる効果があり、カビの抑制に役立ちます。特に北側の部屋や収納など、日当たりの悪い場所こそ小さな窓や高窓を設けて自然光を取り入れると、空気がこもりにくくなります。また、掃除のしやすさを考えた場合も、明るさは汚れの“見える化”につながるため、日中の自然光の入り方を想定した窓設計が大きな意味を持ちます。換気や除湿と合わせて、光の力も上手に活かすことで、より清潔で快適な空間が実現します。
2-5. 日常掃除を習慣化する動線とは
掃除を特別な家事にしないためには、「動線に組み込む」ことがとても有効です。日々の生活の中で自然と掃除ができるような導線設計がされていれば、わざわざ掃除の時間を確保しなくても、家をきれいに保つことができます。掃除しやすい家とは、生活動線と掃除動線が一致している家ともいえるでしょう。
たとえば「玄関から手洗いまでの動線」に沿って、小さな掃除グッズやマットを配置すれば、外から持ち込んだ汚れにすぐ対応できます。また、洗面脱衣室と浴室の近くに掃除用の収納を設けておけば、水まわりの汚れが気になったタイミングでサッと掃除できるようになります。掃除したい場所の近くに掃除道具を収納できる動線計画が、習慣化のカギです。
また、家の中を「回遊できる」ように設計することも、掃除の習慣化にとって大きなメリットになります。キッチン→洗面→リビング→廊下とぐるっと一周できるような間取りは、移動しながら自然に掃除ができる構造ともいえます。掃除機やモップを持って歩きやすく、“ついで掃除”がしやすくなるのです。
動線とともに意識したいのが、「目につく汚れをすぐに掃除できる仕組み」です。リビングのテレビ裏、窓まわり、階段など、汚れが目立ちやすい場所にはハンディモップや除菌シートをサッと取り出せるように設けておくと、汚れを見た瞬間に対応できます。掃除グッズの“定位置”を動線上に設けることで、「あとでやる」が「今やる」に変わります。
最後に、家族全員が掃除しやすい動線を共有できることも大切です。誰か一人に頼らず、家族の誰でも掃除できる仕組みが整っていれば、掃除は習慣として根づきやすくなります。お子さまが自然と掃除に参加できるよう、道具の高さや位置を調整したり、動線をシンプルに保つことで、日常の中に掃除を取り込む文化が育っていきます。動線づくりは、「暮らしやすさ」と「片付けやすさ」をつなぐ設計です。
3. 長く快適に暮らすためのアイデア

3-1. 収納と掃除をセットで考える習慣
家を長く快適に保つためには、収納と掃除を「別々に考えない」ことがとても大切です。片付いていない空間は、どれだけ掃除をしても清潔感が出にくく、また、収納が不十分な場所ほどホコリが溜まりやすくなります。収納と掃除は表裏一体であり、一緒に設計・習慣化することで、暮らしの質は格段に向上します。
たとえば、収納スペースの近くに掃除道具を置くことで、「しまうついでに掃除する」という流れが自然に生まれます。衣類をしまうときにクローゼットの中を軽く拭く、ストック品を補充するときに棚板のホコリを取る——こうした“ついで掃除”の習慣が、結果的に家全体の清潔感を支えるのです。
収納の中身を定期的に見直すことも、掃除とセットで行うと効果的です。物が多く詰め込まれた収納は、ホコリがたまりやすく掃除もしづらくなります。季節の変わり目や年末などに収納の中を整理し、そのタイミングで拭き掃除を行うことで、「整理+清掃」のサイクルが自然と定着します。
さらに、収納そのものの設計も掃除のしやすさを意識すると、日々の管理が楽になります。たとえば、床に置く収納よりも壁付けの吊り戸棚や造作収納の方が、床の掃除がしやすくなり、ホコリの蓄積を防げるようになります。掃除のたびに物をどかす手間を減らす工夫は、長く快適に暮らすうえでとても有効です。
最後に、家族全員が「収納と掃除はセット」と意識することが、住まいを長く保つ最大のポイントです。収納は「しまう場所」だけでなく、「管理する場所」として機能することで、汚れに早く気づけるようになります。片付け=掃除の第一歩と捉え、日常の中に無理なく取り込める仕組みづくりが、持続可能な快適な暮らしを支えてくれます。
3-2. 季節ごとの収納・掃除ルール
日本の暮らしは四季の変化に大きく影響を受けるため、収納や掃除も季節に応じて見直すことが理にかなっています。衣替えや暖房器具の出し入れなど、季節の節目は収納内容をチェックする絶好のタイミングです。これを単なる「入れ替え作業」にとどめず、掃除と整理のルーティンとして定着させることが、清潔で快適な住まいを維持する秘訣です。
春と秋は、気候が穏やかで家の中を整えるのに適した季節です。春は冬物の片付けとともに、暖房器具や加湿器などの掃除と収納を行い、秋には夏の家電や寝具をしっかり乾かしてから収納します。収納前に「掃除」と「点検」をセットにすることで、次のシーズンに気持ちよく使える状態を保つことができます。
冬は換気や掃除がしにくいため、ホコリや湿気対策を意識した収納が求められます。衣類や寝具は湿気を溜め込まないようこまめに干す、収納内に除湿剤を活用するなどの工夫が大切です。また、暖房器具のまわりにはホコリが溜まりやすく、安全面のためにもこまめな掃除が必要です。
夏は湿気とカビが気になる季節です。風通しのよい収納計画や、すのこ・ルーバー扉の活用はもちろん有効ですが、そもそもカビを発生させないためには、高断熱・高気密の住宅性能が非常に有効です。外気の湿気を遮断し、室内の温度と湿度を安定させることで、カビが繁殖しにくい環境を整えることができます。また、エアコンのフィルター掃除やカーテンの洗濯など、見落としがちな場所もこの時期にチェックしておくと、暮らしの質がぐんと上がります。
このように季節に合わせた収納と掃除のルールを作っておけば、「大掃除」の必要がなくなるというメリットもあります。年末だけに集中するのではなく、年間を通して少しずつ整える意識が、住まいを清潔に保つコツです。家族で季節ごとの作業を共有し、「今やること」を明確にすることで、住まいのメンテナンスがもっと身近で続けやすいものになります。
3-3. 収納アイテムと掃除グッズの見直し
長く快適に暮らすには、収納アイテムや掃除グッズも定期的に見直すことが重要です。生活スタイルが変われば、必要な道具や使い方も自然と変化します。昔は便利だと思っていた収納ケースが、今ではストレスの原因になっていることもあるため、「今の暮らしに合っているか」を基準に見直す習慣を持つことが大切です。
特に収納グッズは、「増やす前に、まず見直す」ことが鉄則です。便利そうだからと買い足す前に、本当に必要か、代用できないかを考えることで、収納の無駄やごちゃつきが防げます。また、同じ種類のボックスやカゴで統一すると、見た目が整い掃除もスムーズになるという副次的な効果もあります。
掃除道具も、「どこで・何に使うか」に応じた選び方が重要です。たとえば、階段用の軽いハンディモップや、キッチン用の細口ノズルの掃除機など、場所に合った掃除グッズを揃えることで、日常の掃除が格段に楽になります。また、使いやすい道具は「気づいたらすぐ掃除する」習慣づくりにもつながります。
収納と掃除の連携を高めるには、「収納の中に掃除道具を組み込む」発想も効果的です。たとえば、パントリーの下段にミニ掃除機を、クローゼットの隅に衣類用ブラシを置くなど、行動と一緒に掃除ができる仕組みを作ることで、掃除のハードルは大きく下がります。
最後に、収納や掃除グッズは「減らす」ことも大切です。増えすぎた道具は管理も手間になり、逆に使いにくくなる原因になります。「必要な道具だけが、適切な場所にある状態」を目指すことが、快適で掃除のしやすい住まいづくりの基本です。年に1〜2回は中身をチェックして、不要なアイテムを手放すタイミングを意識すると、暮らし全体がスッキリします。
3-4. 掃除のしやすさを設計に活かす
家づくりの段階から「掃除のしやすさ」を意識することは、暮らしの快適さを左右する大きな要素です。間取りや収納を考えるとき、使い勝手だけでなく日々の掃除動作がスムーズにできるかという視点を取り入れることで、長期的に負担の少ない住まいになります。掃除は毎日のことだからこそ、設計での工夫が生きてくるのです。
掃除のしやすさという視点から見ると、造り付けの造作家具には大きな利点があります。床と家具の間にすき間がなく、ホコリが入り込みにくいため、「そもそもホコリがたまらない」設計が可能になります。また、既製品では生まれがちな無駄なすき間がないため、家具の後ろや下を掃除する必要がなく、日々の掃除の手間を大きく減らしてくれます。
さらに、造作家具は空間にぴったり合わせて設計されるため、見た目がすっきりするだけでなく、掃除道具や日用品をスマートに収納できる工夫も加えやすくなります。たとえば、リビングボードの下にルンバの基地を組み込んだり、パントリー内に掃除グッズ専用の引き出しを作ったりと、掃除を日常に組み込む設計が可能です。これは既製品では実現しづらい、造作家具ならではの魅力です。
また、壁面いっぱいに設計された造作収納は、床にモノを置かない「浮かせる収納」を実現しやすく、床面の掃除が圧倒的にしやすくなります。掃除機やモップの動きもスムーズになり、毎日の掃除が格段にラクになります。見た目の美しさと機能性を両立しながら、清潔な状態を保ちやすい住まいを実現できるのは、まさに造作家具の大きな魅力です。
コンセントやスイッチの位置も、掃除のしやすさに影響します。最近はコードレス掃除機の利用が主流になりつつありますが、それでも充電のための定位置や収納場所は必要です。使用後にすぐ戻せる場所に充電ステーションを設けておけば、「出しっぱなし」にならず、掃除のハードルも下がります。また、コード式の掃除機を使う家庭では、各部屋の中心付近や動線に沿った場所にコンセントがあることで、掃除の手間やストレスを軽減できます。掃除スタイルに合った電源計画を立てることが、無理なく掃除を続けるコツです。
水まわりの掃除も、設計次第で大きく差が出ます。たとえば、洗面台やキッチンに継ぎ目が少ない一体型カウンターを採用すれば、隙間に汚れがたまらず、日常の掃除が格段に楽になります。また、床材や壁材の素材を汚れにくいものにすることも、日々の清潔維持に大きく貢献します。
最後に、家族の誰もが「掃除しやすい」と感じる設計であることが何よりも大切です。掃除のしにくい家は、やがて誰も掃除をしなくなるものです。汚れやストレスが積み重ならない家を実現するために、生活の中に掃除が自然に組み込まれる設計を意識することが、長く快適に暮らすための最もシンプルで確実な方法です。
3-5. 家族で維持する住まいの清潔習慣
清潔な住まいを長く維持するためには、誰か一人に頼るのではなく、家族全員が掃除を「自分ごと」として共有することが大切です。掃除を担当制にするのではなく、日常の中で気づいた人が自然に手を動かせるような雰囲気があると、家全体の清潔感が安定して保たれます。
そのためには、掃除道具の場所や使い方を家族みんながわかるようにしておくことが基本です。たとえば、リビングに置いたハンディモップの定位置を決める、子どもでも使える軽い掃除グッズを用意するだけでも、参加のハードルがぐっと下がります。
子どもにとっても掃除は大切な生活教育の一部です。小さなころから「汚れたら拭く」「モノを戻す」といったシンプルな行動を習慣にできれば、大人になってからも自然と片付けや掃除が身についているものです。掃除を親子で一緒に楽しむ時間として取り入れるのも良い方法です。
また、ルールよりも習慣を優先することも大切です。細かい当番制を決めるより、「朝の支度のあとに一拭きする」「ゴミの日の前にリビングを見直す」など、暮らしに自然と組み込める形が理想です。掃除を“家事”ではなく“日常の一部”にすることが、無理なく続けられるコツです。
最後に、掃除や整理整頓ができたことを家族で喜び合うことも、住まいの清潔を保つモチベーションになります。「きれいになったね」「ありがとう」と声をかけ合うだけでも、心地よい空気が家庭の中に生まれます。家族で維持する清潔習慣は、単なる作業の積み重ねではなく、暮らしそのものの質を高める習慣です。
まとめ

家づくりで本当に大切なのは、見た目の美しさや広さだけではなく、「日々の暮らしが自然と整う仕組み」をつくることです。この記事では、収納と掃除を軸に、そうした暮らしの基盤を築くための考え方をお伝えしました。
【収納編】 収納は“とりあえず詰め込む場所”ではなく、“暮らしを整える拠点”です。天袋や床下収納のような使いにくい場所は避け、日常動線と連動した収納を設計することが、ストレスなく片付いた家を保つ鍵になります。また、物の量を把握し、断捨離の習慣を持つことも重要です。
【掃除編】 掃除は「やらなきゃ」ではなく、「ついでにできる」工夫が続く秘訣です。家具の配置や段差の解消、掃除道具の配置を見直すことで、自然と掃除がしやすい家になります。特に、高断熱・高気密住宅のような性能を活かした換気計画は、カビやホコリの原因を根本から抑えてくれます。
【習慣と設計編】 掃除や整理整頓を「家族全員で自然に続けられる設計」にしておくと、誰か一人に負担が偏ることなく、暮らしが整います。造作家具のような、掃除しやすさを意識した設計や、子どもが手に取りやすい収納、ルンバ基地のあるテレビ台など、暮らしにフィットした住まいは毎日をラクにしてくれます。
最後に、ぜひ「一つでもできそうなこと」から取り入れてみてください。 大きなリフォームや家づくりのタイミングでなくても、小さな気づきと改善の積み重ねが、快適な暮らしを生み出してくれます。住まいは“暮らしの道具”です。あなたらしい整った暮らしのヒントが、この記事に一つでも見つかっていれば嬉しいです。