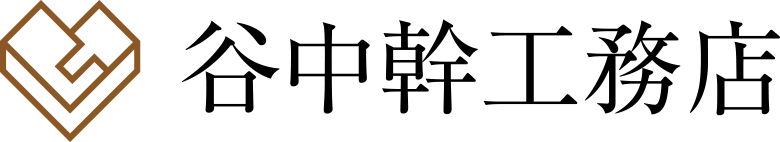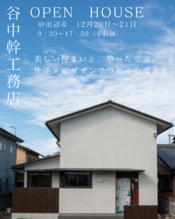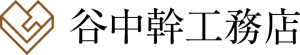初心者でもわかる住宅の換気完全ガイド|第一種・第三種・24時間換気を徹底解説!

目次
「最近なんだか家の中の空気が重い」「冬は窓の結露がひどくてカビが心配」「子どもが咳き込むけど原因がわからない」──そんな小さな違和感が、実は“換気不足”から来ていることをご存知ですか?
近年の住宅は高気密・高断熱化が進み、快適に見える一方で、空気がよどみやすく、湿気や有害物質がたまりやすいという課題も抱えています。その結果、健康被害や住まいの劣化といった深刻な問題につながることもあるのです。
本記事では、第一種・第二種・第三種という3つの換気方式を比較しながら、それぞれの特徴と選び方、設計・施工・リフォーム・メンテナンスに至るまでを、初心者にもわかりやすく丁寧に解説しています。
「うちはどの方式が合っているのか?」「換気設備のメンテナンスって何をすればいいの?」といった疑問が、この記事を読むことでスッキリと解消されるはずです。健康・快適・省エネを両立した“呼吸する住まい”を手に入れるヒントが、ここにあります。
今こそ、ご自宅の“空気の質”を見直してみませんか?
この記事で得られる5つの答え
住宅の換気は「自然任せ」ではなく「計画的に管理すること」が必要です。高気密・高断熱化が進む現代の住宅では、意図的な換気設計が欠かせません。
第一種・第二種・第三種換気の特徴と、自分に合った方式の選び方が理解できるようになります。暮らし方や地域の気候に合わせて、最適な方式が見えてきます。
換気効果を高めるには、気密・断熱性能と空気の流れを意識した設計が重要です。設備だけでなく、住まいの構造と暮らし方も換気性能に大きく影響します。
メンテナンス(フィルター清掃・湿度管理)を怠らないことで、換気性能を維持できるという意識が身につきます。健康的で快適な空気環境を保つには、日々のケアが鍵です。
新築・リフォームの換気計画の違いと、快適性を損なわない暮らし方の工夫がわかります。どの段階の住まいでも、適切なアプローチで換気性能を高めることが可能です。
1. 換気の基礎知識を身につけよう
1-1. なぜ住宅に換気が必要なのか
私たちが生活する住宅は、見た目以上に「密閉された空間」です。窓を閉め切り、冷暖房を効かせる現代の暮らしでは、空気がこもりやすくなっています。そのため、外から新鮮な空気を取り入れ、室内の汚れた空気を外に出す「換気」がとても重要になります。
換気が行われないと、私たちの呼吸や調理、洗濯、入浴などで発生する湿気や二酸化炭素、さらにはホルムアルデヒドなどの有害物質が室内に溜まってしまいます。これらは目には見えませんが、健康に大きな影響を与える原因となります。
特に冬場は、結露やカビの発生リスクが高まる時期です。適切な換気がされていないと、窓まわりや押し入れ、クローゼットの中などに湿気がたまり、カビの温床となります。これは建物の寿命を縮める原因にもなりかねません。
さらに、感染症対策としても換気の重要性が注目されています。新型コロナウイルスの流行以降、「こまめな換気」が広く推奨されるようになりました。空気中のウイルスや細菌を外へ逃がす役割が、住宅の換気にはあるのです。
このように、換気は「住まいの健康」と「人の健康」の両方を守る基本的な要素です。日常生活の中で意識されることは少ないかもしれませんが、実はとても大切な役割を担っているのです。
1-2. 換気不足がもたらすリスクとは?
換気が不足すると、住宅内の空気環境は急激に悪化します。空気中に含まれる湿気や化学物質が滞留し、目に見えない汚染物質が増加するからです。これらは私たちの健康を静かに蝕む原因になります。
たとえば「シックハウス症候群」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは新築やリフォームした住宅において、建材などから発生する化学物質が室内にこもり、頭痛や目まい、喉の痛みなどの症状を引き起こすものです。
また、換気が不十分な環境ではカビやダニが発生しやすくなり、アレルギーや喘息の原因にもなります。特に子どもや高齢者にとっては、その影響はより深刻です。健康に配慮した住まいを維持するには、換気は欠かせません。
換気が不十分な状態は、建物の寿命にも悪影響を及ぼします。湿気がこもることで木材が腐食しやすくなり、住宅の構造にダメージを与える可能性があります。さらに断熱性能も低下し、光熱費の増加にもつながります。
このように、換気不足は単に「空気がこもっている」というレベルの問題ではありません。健康被害、建物の劣化、エネルギー効率の低下など、さまざまな問題が連鎖的に発生するリスクを抱えています。だからこそ、日常的な換気対策が必要不可欠なのです。
1-3. 住宅における空気の流れの基本
換気を効果的に行うためには、「空気の流れ」を正しく理解することが大切です。住宅における空気の流れは、基本的に「給気」と「排気」のバランスで成り立っています。外から新鮮な空気を取り入れる「給気」と、室内の汚れた空気を外に出す「排気」の両方が機能して初めて、快適な空間が保たれます。
空気は「低いところから高いところへ」「暖かい空気は上に、冷たい空気は下に」という自然の法則に従って流れます。例えば冬場は暖房により上部に暖かい空気がたまり、夏場は窓を開けても空気が停滞することがあります。こうした特性を理解し、適切な位置に換気口を設置することが大切です。
また、風の通り道を考慮した「対面換気」は非常に効果的です。たとえば、家の北側と南側に窓や通風口を設けることで、風が通り抜けやすくなります。これは自然換気の基本的な設計手法であり、住宅全体の空気の質を高めるためにも有効です。
ただし、窓を開けての換気だけでは限界があります。住宅密閉性が高い現代住宅では、自然換気に頼るだけでは十分な換気量が確保できません。そのため、機械的な換気設備との併用が求められます。これにより、風のない日でも安定した換気が可能になります。
空気の流れを意識した住宅設計は、快適性や省エネ効果にも直結します。冷暖房の効率が良くなり、電気代の削減にもつながるからです。住まいの中で空気がどう流れるのかを意識しながら、効果的な換気プランを立てることが、長く快適に暮らすための第一歩です。
1-4. シックハウス対策としての換気法
「シックハウス症候群」は、住宅内の空気汚染によって引き起こされる健康被害のことです。主な原因は、建材や家具から放出されるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)や、カビ、ダニなどのアレルゲンです。これらを抑えるために、換気はとても重要な役割を果たします。
シックハウスを防ぐには、まずは有害物質を出さない建材を選ぶことが基本ですが、それだけでは完全に防げません。新築やリフォーム直後は特に、空気中に化学物質が多く含まれていることがあるため、計画的かつ強制的な換気が求められます。
換気対策として有効なのは「24時間換気システム」の導入です。これにより常に空気の入れ替えが行われ、化学物質の濃度が上がりすぎることを防げます。特に第一種換気や第三種換気といった機械換気方式が効果的です。
近年では造作収納の増加や家具のミニマル化により、住宅内における化学物質の発生源は以前より少なくなってきています。しかし、それでも建材や接着剤などからのVOCは完全には避けられません。そのため、住まい全体で空気が滞らないように、給気口と排気口の配置や室内の空気の流れを設計段階から意識することが重要です。これにより、局所的な汚染の偏りを防ぎ、安定した空気環境を保つことができます。
自然換気は一見手軽で取り入れやすい方法に見えますが、気温や風向きなどの外的条件に左右されるため、安定した換気効果を得るのは難しいという限界があります。特に空気の流れが悪い日や夜間などは、十分な換気が行われないことも多いです。そのため、シックハウス対策としては、自然換気に頼るのではなく、機械換気を併用することが非常に重要です。特に24時間換気システムを導入することで、気象条件に関係なく、一定の空気環境を保つことができます。
1-5. 法律で定められた24時間換気義務とは
日本では2003年に建築基準法が改正され、新築住宅には「24時間換気システム」の設置が義務づけられました。これは、シックハウス症候群の対策として導入された制度で、住宅内に有害な化学物質が滞留しないようにするための法律です。
法律では、建物全体の空気が1時間に0.5回以上入れ替わる性能が求められています。つまり、2時間で室内の空気がすべて新しくなるような換気が、常時行われていなければならないということです。この基準を満たすには、計画的な換気設備の設置が必要となります。
この24時間換気義務は、特に高気密・高断熱住宅において重要です。気密性が高い住宅では、計画的な換気がしやすくなる一方で、隙間風による自然換気には頼れないという側面があります。従来のように隙間からの空気の出入りが期待できないため、給気と排気のバランスを整えた換気システムの設計が不可欠です。これにより、快適かつ安全な空気環境を維持することができます。
一方で、住まい手がこの設備の重要性を理解せず、スイッチを切ってしまったり、給気口を塞いでしまうケースもあります。これではせっかくの換気設備も本来の効果を発揮できません。法律で義務づけられているという意識を持ち、日常的に正しく運用することが大切です。
また、換気設備は設置すれば終わりではありません。定期的なフィルター清掃や動作確認が必要です。フィルターが詰まっていたり、ファンが故障していた場合、十分な換気が行われなくなります。法律を守るだけでなく、自分たちの健康を守るためにも、換気設備のメンテナンスは欠かせません。
2. 換気の種類とその特徴を理解する
2-1. 第一種換気とは?仕組みとメリット・デメリット
第一種換気とは、「給気」と「排気」の両方を機械(ファン)で制御する換気方式です。住宅内の空気の流れをすべて機械で管理するため、もっとも計画的で安定した換気が実現できます。高気密・高断熱住宅との相性も非常によく、近年では高性能住宅を中心に採用が進んでいます。
この方式の最大の特徴は、「熱交換型」の機器が導入できることです。外気をそのまま室内に取り込むのではなく、排気される室内の空気から熱(暖かさ・冷たさ)を回収してから、新鮮な外気に移して取り込む仕組みです。これにより、冷暖房のロスを最小限に抑え、省エネ性も高くなります。
また、花粉や黄砂、PM2.5などの有害物質の侵入を防ぐために、給気口に高性能フィルターを設置することも可能です。外気の質が気になるエリアでも安心して換気できるというのは大きな魅力です。アレルギー体質の方や、小さなお子様がいる家庭には特におすすめです。
一方で、設備のコストやランニングコストがかかるというデメリットもあります。給排気の両方にファンを設置する必要があるため、初期費用が高くなりがちです。また、フィルターや機器のメンテナンスも定期的に必要で、手間がかかると感じる方もいるかもしれません。
さらに、ダクトを使って各部屋に空気を送る「ダクト式」と、部屋ごとに個別のユニットを設ける「ダクトレス式」があり、設計や間取りによって最適な方式を選ぶ必要があります。ダクト式は配管スペースが必要なため、設計初期からの計画が欠かせません。リフォーム時の導入はややハードルが高くなる傾向があります。
第一種換気システムの中には、顕熱だけでなく潜熱(湿度)も交換可能な「全熱交換型」と呼ばれるタイプもあります。これは、外気を取り込む際に温度だけでなく湿度も調整できるため、冬の乾燥や夏の湿気をやわらげ、より快適な室内環境を実現します。冷暖房効率の向上だけでなく、湿度管理までできる点は、特に四季のある日本の住宅にとって大きなメリットです。
2-2. 第二種換気とは?主にどんな場面で使われるのか
第二種換気とは、「給気は機械で行い、排気は自然に任せる」という方式の換気です。第一種換気と同様に給気側にファンを設置しますが、排気は排気口から自然に抜けるように設計されており、住宅ではあまり採用されない方式です。
この方式の最大の特徴は、室内の気圧を外よりも高く保てるという点です。室内に常に新鮮な空気を押し込むことで、外気の侵入を防ぎ、清潔な空間を維持することができます。そのため、病院の無菌室や食品工場、クリーンルームなど、高い衛生環境が求められる空間で多く採用されています。
第二種換気は、給気を機械で行い、排気を自然に任せる方式であり、室内が正圧状態になります。このため、外気の侵入を防ぐ効果がありますが、排気が自然換気に依存するため、湿気や汚れた空気が室内に滞留しやすくなります。特に冬季には、室内の湿気が壁内や天井裏に入り込み、冷えた部分で結露が発生しやすくなります。結露はカビの発生要因となり、建材の劣化や健康被害を引き起こす可能性があります。したがって、住宅で採用する場合には、湿度管理や断熱対策を十分に行う必要があります。
また、排気が自然に行われるという特性上、住宅の立地や気象条件によっては排気効率が不安定になることもあります。風が強い日や逆流が起きるような場所では、思うように空気が排出されないことがあり、室内環境が不快になる可能性も否定できません。
そのため、住宅で第二種換気を採用することはまれであり、用途を明確にしないまま導入すると、かえって室内環境が悪化するリスクがあります。もし採用する場合は、気圧コントロールが必要な特別な住宅(防音室、試験室など)に限定されるべきです。一般住宅では、第一種または第三種換気が基本となります。
2-3. 第三種換気とは?特徴と注意点
第三種換気とは、「排気を機械で行い、給気は自然に任せる」換気方式です。つまり、排気ファンを使って室内の空気を外へ押し出す一方、給気は外壁の給気口などから自然に取り込むスタイルとなっています。住宅において最も多く採用されている換気方式の一つです。
この方式の大きなメリットは、コストの低さと構造のシンプルさにあります。給気にファンを使わないため、設備費もランニングコストも抑えられます。設計の自由度も高く、リフォーム時にも導入しやすい方式として広く普及しています。
ただし、給気が自然まかせであるため、外気温や風向き、気圧などの環境条件に大きく左右されやすいというデメリットもあります。寒冷地では冷気がそのまま室内に入ることもあり、快適性に影響を与える場合があります。
また、給気口の位置が不適切だったり、メンテナンスが不十分な場合には、外気が十分に取り込めず、室内が負圧になってしまうことがあります。これにより、すきま風や外からの臭気の逆流、ドアの開閉不良といった不具合が発生することもあります。
さらに、給気口にフィルターがない(または簡易的なものしかない)場合、花粉やPM2.5といった有害物質の侵入リスクが高まります。これを防ぐためには、定期的なフィルター清掃や高性能フィルターの後付けなどの工夫が必要になります。
そのため、第三種換気を採用する場合は、「自然給気の限界」を理解したうえで、配置・開口部の設計、断熱性とのバランスをしっかり考慮することが重要です。適切に運用すればコストパフォーマンスの高い換気方式となりますが、過信は禁物です。給気・排気の流れを正しく設計し、必要に応じて補助的な工夫を取り入れることが、快適な住環境を維持する鍵となります。
2-4. 3つの換気方式の比較と選び方
第一種・第二種・第三種の3つの換気方式には、それぞれ異なる特徴と向いている用途があります。選ぶ際には単に「性能」や「価格」だけでなく、住宅の構造や家族構成、生活スタイル、地域の気候条件など、多くの要素をバランスよく考慮することが大切です。
第一種換気は、最も高性能で安定した換気が可能な方式です。給気・排気の両方を機械制御でき、熱や湿度の回収もできるため、快適性・省エネ性の両立が可能です。ただし、初期費用やメンテナンスコストが高く、設計段階からの計画が求められるため、新築や高性能住宅向けといえます。
第二種換気は、特殊な環境で求められる正圧管理が可能で、清潔な空間を維持できますが、住宅用途には向きません。湿気や結露、排気の不安定さといった課題があり、一般住宅では原則非推奨とされています。医療施設や実験室など、特定用途に限られる方式です。
一方、第三種換気はコストパフォーマンスに優れ、戸建て住宅や集合住宅でも多く採用されています。特に、比較的温暖な地域や予算を抑えたい場合に適しています。ただし、自然給気に頼るため外気温や風向きの影響を受けやすく、設計の工夫や定期的なメンテナンスが重要です。
換気方式を選ぶ際には、「性能・コスト・快適性・メンテナンス性」の4つの視点から比較することが重要です。たとえば、省エネ性を重視するなら第一種、施工の簡便さや費用重視なら第三種、特殊用途なら第二種といった具合です。状況に応じて柔軟に判断しましょう。
また、どの方式を選ぶにしても、設計段階からの計画が極めて重要です。給気・排気の位置、風の流れ、各部屋の使用目的などを踏まえて、全体としてムラのない空気の流れを作ることが快適性と健康につながります。プロとの相談の中で、ライフスタイルに合った最適な方式を導き出すことが理想的です。
2-5. ライフスタイル・地域別に考える最適な換気方式
換気方式の選定は、単に住宅性能だけでなく、「住む人のライフスタイル」や「地域の気候条件」によっても最適解が変わってきます。たとえば、在宅時間が長い家庭と短い家庭、都市部と自然豊かな地方とでは、求められる空気環境や設備の役割も異なるのです。
在宅時間が長い・短いにかかわらず、室内の空気環境を常に一定に保ちたいと考える方には、第一種換気が適しています。給気・排気の両方を機械で制御することで、温度・湿度・空気の流れを安定させることができ、アレルギー対策や健康維持に有効です。ペットのいる家庭や、空気質に敏感な家族がいる場合にも安心感があります。
一方で、第三種換気は構造がシンプルで、コストを抑えつつ一定の換気効果が得られる方式です。自然給気を前提とするため、設計段階で給気口の配置や空気の通り道をしっかり計画することが重要です。寒冷地や多湿地域ではデメリットもあるため、地域の気候条件をよく考慮する必要があります。
また、寒冷地に住む方にとっては、熱損失を抑えた換気方式が非常に重要です。第一種の熱交換型換気を採用することで、室温を保ちながら新鮮な空気を取り入れることができ、光熱費の節約にもつながります。断熱性の高い住宅と組み合わせることで、その効果はさらに高まります。
地域によっては、外気の質にも注意が必要です。たとえば、都市部や交通量の多い地域では、花粉やPM2.5といった有害物質が多く含まれている場合があり、高性能フィルターが使える第一種換気が適しています。逆に空気のきれいな郊外では、第三種で十分なこともあります。
このように、「どの換気方式が一番良いか」ではなく、「誰が、どこで、どのように暮らすか」という観点から換気を考えることが大切です。暮らしに合った換気計画は、快適性だけでなく、健康・省エネ・住まいの寿命にも関わってくる重要な要素です。住宅の設計段階から、しっかりと換気について相談しておくことが理想的です。
3. 実際の換気計画とメンテナンス
3-1. 換気設備の設置場所とレイアウトの考え方
換気計画を成功させるためには、「どこに給気口・排気口を設けるか」が非常に重要です。空気は目に見えないものですが、その流れが室内環境の快適さや清潔さに大きく影響します。設計段階から換気の流れを意識し、計画的に配置することが求められます。
基本的な原則としては、「きれいな空気を取り入れて、汚れた空気を排出する」という流れを住まいの中に作ることです。たとえば、給気口はリビングや寝室などの居室に、排気口はトイレ・脱衣所・キッチンなどの水まわりや臭気がこもりやすい場所に設けるのが理想です。
空気の流れは直線的ではなく、家具の配置や間取りによって妨げられることがあります。そこで、建物全体の空気の流れをシミュレーションすることが重要です。断熱や気密の性能と組み合わせることで、冷暖房効率を損なわずに空気をスムーズに循環させる工夫が可能になります。
特に注意したいのは、給気口の位置と高さです。冬場に冷たい外気が直接身体に当たると不快に感じるため、人の頭や身体に風が直接当たらない位置に設置することが大切です。逆に排気口は、湿気や臭気がこもりやすい天井近くや壁上部が適しています。
近年では、ダクト式とダクトレス式の選択肢もあり、それぞれに設置条件が異なります。ダクト式は天井裏などのスペースが必要であり、新築住宅に向いています。一方、ダクトレス式はリフォームにも対応しやすく、設置の自由度が高いため、既存住宅でも換気性能を高めたい方に適しています。
最後に重要なのは、「メンテナンスのしやすさ」を考慮した設置です。フィルターの掃除や換気扇の点検を定期的に行うには、手が届きやすく、作業がしやすい場所であることが望まれます。設計段階でメンテナンスまで想定しておくことが、長く快適な空気環境を維持する秘訣です。
3-2. フィルター清掃やメンテナンスの重要性
換気設備は設置して終わりではありません。適切なメンテナンスを継続的に行うことが、その性能を最大限に発揮させ、住宅の空気環境を快適に保つためには不可欠です。特に、フィルターの清掃や交換は基本中の基本であり、怠ることで多くの問題が発生します。
フィルターには、外気からの花粉・ホコリ・虫・PM2.5などの微細な粒子が集中的に溜まります。放置すると目詰まりを起こし、給気・排気の風量が著しく低下して、換気本来の効果が発揮できなくなってしまいます。また、機械の故障の原因になることもあります。
目詰まりしたフィルターのまま運転を続けると、消費電力が増え、電気代の上昇や設備寿命の短縮といった経済的なデメリットも生まれます。さらに、空気がきれいにならないどころか、汚染物質が逆流するリスクもあり、健康被害につながる可能性もあります。
フィルターの掃除は一般的に1〜3か月に一度、製品によっては半年ごとの交換が推奨されているものもあります。各機器の取扱説明書を確認し、季節の変わり目や花粉の多い時期などは特に注意してメンテナンスを行うことが望ましいです。
また、ファンやダクトの内部も定期的な清掃が必要です。特に油を多く使うキッチン周辺では、換気扇やダクト内に汚れが蓄積しやすく、放置すれば風量の低下や異音、悪臭、さらには火災の原因になることもあります。ユーザー自身がこまめに状態を確認し、必要に応じて掃除を行うことで、換気設備の性能を長く維持することができます。
3-3. 換気性能を高めるための住まいの工夫
換気性能をより効果的に発揮させるためには、単に設備を導入するだけでなく、住まいの設計や暮らし方にも工夫を取り入れることが大切です。空気の流れを遮らないレイアウト、湿気がこもらない収納方法、開放感のある間取りなど、日常の環境づくりが換気効率に影響を与えます。
まず重要なのは、「空気の通り道」を意識した家具配置です。家具や収納棚の配置次第では、空気の流れが遮られ、換気の効果が十分に発揮されなくなることがあります。空気がスムーズに動ける開放的な動線を意識することで、設備の性能を活かした効果的な換気が実現できます。
次に、収納スペースの通気性も大切です。押し入れやクローゼットは湿気がこもりやすく、放置するとカビの原因になります。すのこを使ったり、定期的に扉を開けて空気を入れ替えることで、湿気を逃しやすくなります。さらに、除湿剤を併用することで効果が高まります。
室内ドアの下部にアンダーカット(隙間)を設けるのも効果的な方法です。ドアを閉めた状態でも空気が流れるようにすることで、部屋ごとの空気が滞らず、住宅全体で効率的な換気が実現します。特に第三種換気を採用している場合は、このような小さな工夫が換気効果を大きく左右します。
また、屋内外の温度差や風向きを活用することも重要です。たとえば、南北に窓があると自然換気しやすく、風が通り抜ける環境になります。換気設備とあわせて自然の力も活用できれば、より効率的で快適な住まいとなります。計画換気と自然通風のバランスをとることが理想です。
3-4. 新築時とリフォーム時で異なる換気の注意点
換気計画は、新築とリフォームで大きくアプローチが異なります。新築では設計段階から換気経路や設備配置を自由に計画できますが、リフォームでは既存の構造やスペース、開口部の制約があり、理想通りの換気を実現するのが難しいケースも少なくありません。
新築の場合、給気・排気の位置関係や空気の流れを間取りと連動して設計できるのが大きな利点です。第一種換気のようにダクトを必要とするシステムでも、天井裏や壁内に余裕を持たせた設計が可能なため、美観を損なわずに高性能な換気計画が実現できます。
一方、リフォームでは既存の天井高や構造材が制約となり、ダクト式の第一種換気などの導入が難しいことがあります。そのため、後付けできるダクトレスの第三種換気や、個別ユニット型の熱交換換気など、柔軟なシステム選びが必要になります。
また、リフォームでは気密性能が不十分なまま換気設備を導入してしまうと、想定通りの換気量が確保できないことがあります。特に築年数の古い住宅では、隙間の多さが換気性能を著しく低下させる原因となるため、しっかりとした気密を確保するにはフルリノベーションが必要になるケースもあります。気密測定を行ったうえで、必要に応じて建具や断熱材の総入れ替えを検討することが、確実な換気効果を得るための前提条件です。
さらに、リフォームでは居住しながら工事を行う場合も多く、工期の短縮や騒音対策などの施工上の配慮も求められます。設備選定だけでなく、施工のしやすさや将来的なメンテナンス性までを見据えた設計が、住みながら快適な空気環境を手に入れるためのポイントとなります。
3-5. 快適性を損なわない換気:音・風・湿度の調整術
換気は健康と住まいを守るために不可欠ですが、「音」や「風当たり」、「乾燥や湿気」といった要素で快適性を損なってしまうケースもあります。日常生活でのストレスを減らすためには、細かな点にも配慮した設計と運用が求められます。
まず気になるのが「換気音」です。特に第一種換気で使用されるファンの動作音が気になる方も少なくありません。寝室や書斎など静けさが求められる空間では、低騒音タイプのファンを選ぶ、機械本体を居室から離れた位置に設置するなどの工夫が有効です。
次に「風当たり」への配慮です。給気口の位置や形状によっては、外気が直接身体に当たって寒さや不快感を与えることがあります。人が長時間過ごす場所に直接風が来ないようにする配置や、風を分散させるディフューザーの使用が効果的です。
換気と切り離せないのが「湿度」のコントロールです。冬は乾燥、夏は多湿と、日本の気候は1年を通じて湿度の変動が大きいため、全熱交換型の換気システムを導入することで、温度とともに湿度も調整できる環境をつくることが可能です。
さらに、加湿器・除湿機と換気設備を併用することで、空気の入れ替えだけでなく、室内の体感環境をきめ細かくコントロールできます。湿度はカビやウイルスの発生にも直結するため、温湿度計を設置して最適な数値を保つ習慣も大切です。