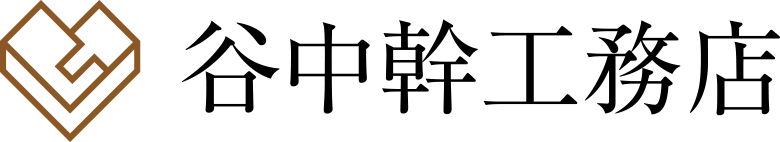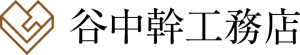ラワンベニアとラワンランバーコアでつくる建具や家具 仕上げはオスモクリア仕上げ


内装の仕上げに用いられる材料には、無垢材などがありますが、べニアも侮れません。
べニアといくとネガティブな印象を受けるかもしれませんが、無垢材を薄く加工したものですので
表面は無垢材となります。今回のテーマはそんな『ベニア』についてです。
ベニアとは プリント合板との違い
通称ベニアは1907年頃 浅野吉次郎が独自に回転式単板切削機を発明し、
単板をニカワで接着したものを『アサノ合板』『ベニア板』として販売した時の用語の名残。
“出典 木造建築用語辞典”
つまり丸太を桂むきのようにうすくスライスしたものを木の向きを直交するように
張り合わしたものとなり、一般的にベニアと呼ばれるものは厳密にはベニア合板となります。
その材料(木材)がラワンならラワンベニア シナならシナベニアとなります。
ベニアというと新建材となりますが、実は無垢の木材が使われているのです。
その点プリントベニアは木目や柄を印刷したものを表面に使ってますのでそこが大きく違う点です。
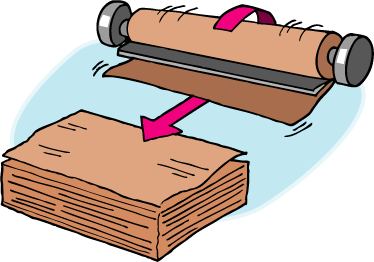
木の丸太を大根のかつらむきのように剥きます。 秋田プライウッドさまH・Pより
ラワンベニアの表面の仕上げ方
ラワンベニアは一般的に下地に使われる材料ですが、昔から建築家さんは仕上げに使用している素材です。
住宅の建築家の王道ともいえる吉村順三さんも好んで使ってらっしゃってたのが有名です。
以前建築中のお家のラワンベニアの表面の仕上げ方を悩んでいた時に会う方会う方に
ご挨拶代わりに!?『ラワンベニア』の仕上げ方はどうされてますか?
とお伺いしていました。
その結果、八割方がオイル系のクリア仕上げとのお答え。
サンプルでクリア仕上げのもと着色仕上げのものをつくって住まい手と
検討した結果、オスモのクリア仕上げという一番得票を集めた
仕上げとなりました。
その時に製作したベットのバックボードを兼ねた本棚がこちら。
この面がベッドのバックボード側。ラワンベニアを仕上げに使用しています。
これは特に良いモノが手に入りました。まだ仕上げをする前でこの綺麗さ。
こういうのがコンスタントに手に入ると良いのですが・・・

で裏側が本棚。こちらはラワンランバーコアといわれるパネル状のものです。
この本棚で寝室と書斎スペースをゆるやかに分けるのが狙いでした。
すこし白っぽいですが、ラワンベニアが良すぎました。相手が悪い(笑)
このあと、可動棚が組みこまれました。

完成したのがこちら。このお家は建具もラワンベニアで製作しましたが
今見ても本当に良いモノが手に入っています。

ラワンベニアを採用する場合の注意点
ラワンベニアは下地材をお書きしました。ラワンベニアを採用する場合の注意点は
下地材がゆえに綺麗な赤いモノが揃えにくい点です。
なるべく赤く、綺麗なものを選別はしていますが、ロットによって色もまちまちで
最近では白っぽいものが増えてきているのも悩みの種です。手前の建具と奥の建具
同じラワンベニアですが、少し色目は変わっています。
この色目の違いを許容できる方でないと難しい仕上げとなってきているのかもしれません。

ラワンベニアをつかった建具 手前は特に赤く仕上りました。

ラワンベニアを使った建具
玄関収納もラワンランバーコアで製作しました。正面に見える建具は杉赤身材をつかった建具ですが
相性もよくて好きな組み合わせのひとつです。

ラワンべニアの施工例でご紹介したお家の施工画像 『タタミリビングの家』
まとめ
綺麗なラワンベニア仕上げを見ると採用したい気持ちがフツフツと湧いてきますが
赤っぽいのが無くなってきたり、色目が揃えにくいのが悩み所です。
白っぽいものを染色仕上げするか?というもの選択肢になってきています。
その点シナベニアは色目に関して安定しているのが魅力です。これらも模索は続きそうです(笑)
シナベニアについてまとめた記事はこちら
メルマガ 【ほぼほぼ日刊 暮らしづくりメルマガ】を始めてます
もっと早く、もっと本音で?! 家づくり、暮らしづくりの情報をお届けしたいとの思いからです
登録はメールアドレスのみ。
【ほぼほぼ日刊 暮らしづくりメルマガ】 メルマガ登録はこちら↓↓↓
特典小冊子をプレゼントいたします。